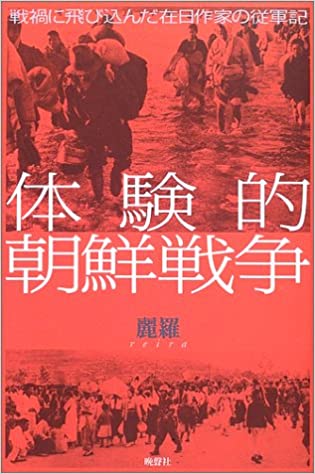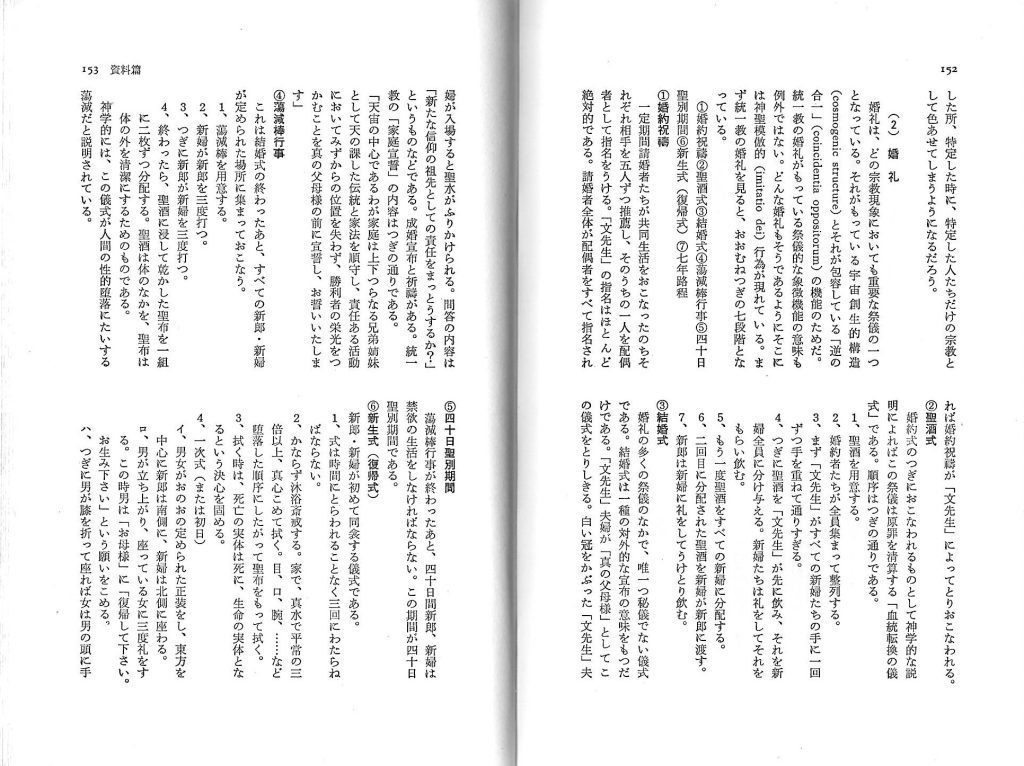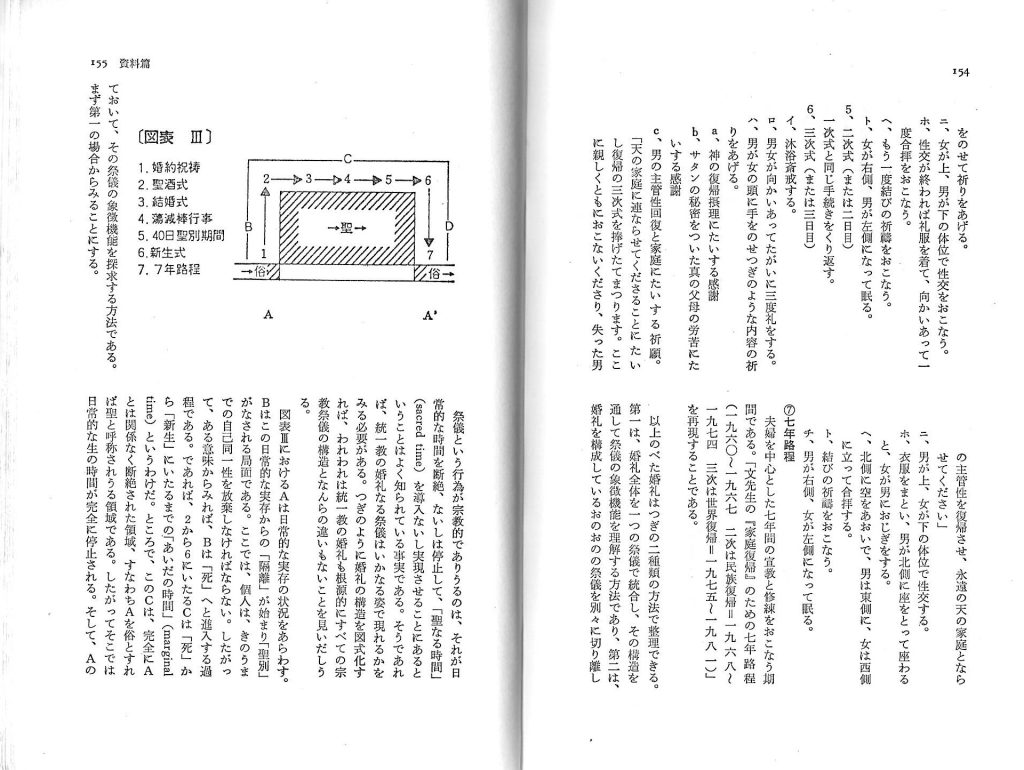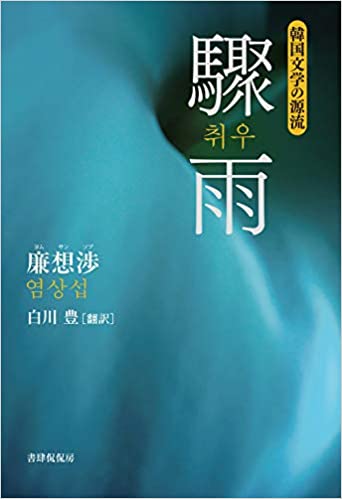麗羅という在日作家(1924-2001)の『体験的朝鮮戦争』という小説を読んだ。1992年の作品。
1945.8.15に日本が降伏し(光復節)てからの3年、1948.9.9に朝鮮民主主義人民共和国が発足し分断体制ができあがるまでの朝鮮半島は、混乱の時代だった。南半分では独立・革命への強い欲求を米軍がむりやり押し止めていたとも言える。
朝鮮の独立については1945.12月米英ソ三国外相によるモスクワ協定で、朝鮮米ソ合同委員会および臨時朝鮮政府の設立が決まっていた。そして米ソ共同委員会が開かれ、過渡政府樹立のためのプランも発表された(46.3.20)。しかし米ソの意見の違いは大きく共同委員会は休会となる。
1947.10.30国連総会は朝鮮への国連の委員団を派遣することを決定した。(ソ連はこの上呈自体をモスクワ協定違反として反対。)p116
委員団はソウル到着後、3/31までに南北同時に総選挙を実施する、それにより朝鮮国民政府を樹立するための議会をつくる、などと発表した。しかし、ソ連及び左派はこれに賛同せず南北同時選挙は実行できなかった。
75年後(分断されたまま)の今日から振り返る場合、仮に実行していたらどうだっただろうかと考えてみることは、できる。
当時の朝鮮全体の人口は約3000万人、北1000万、南2000万と考えてよい。
ソ連と北の指導者は、勝利する自信がなかったから、総選挙に反対したと麗羅は書いている。p121
しかし南では左翼に対する支持の方がかなり圧倒する可能性があった。であれば合計でも勝てる可能性があった。
しかしその場合も、南での左翼支持勢力が北での左翼支持勢力を上回った場合、左翼(共産主義陣営)の指導権は南の指導者に握られる。また北での左翼を支持しない勢力がかなり多かった場合も面目を失う。ソ連および金日成にとってはいずれにしても避けなければならない、と判断された。
朝鮮民族全員の民意を素直に問えば左派が勝利していた可能性がかなりあったのに、金日成は自己権力の維持を第一目標とする考えであったため、それをやろうとしなかった(と言えるだろうか)
今にして思えば、全国同時選挙をやっておきさえすれば、分断をさけることができたのでは、といった思いを抱く人があるだろう。その場合、金日成体制をさらに覆していくことも必要になる。(日本人でしかない私がとやかく言うことではないが)
歴史に対してこのような感想を付け加えるのは、まあ愚かなことである。しかし朝鮮戦争休戦後69年も経つのに、停戦すらできず、統一の目処も立っていないのは不条理すぎる。自分に引きつけて考えようとすると愚痴にならざるをえない。
なぜこんなことになってしまったのか。そしてそれがこんなにも長く続いているのか。その嘆きは麗羅のものでもあった。
朝鮮共産党の指導者朴憲永たちの振る舞いも、こう振る舞っていれば歴史はこうはならなかったはずだ、といいたくなるところが二つある。
「開放直後は、朴の率いる南の朝鮮共産党(ソウルに本部)が主流で、北(平壌)に本部の党は分局に過ぎなかった。それが北労党と南労党になってからは双方の立場が対等になり、モスクワの指令で南北が合党して朝鮮労働党になってからは、北派が主で南派は従といった力関係になってしまった。
朴憲永は、年齢、学識、理論、共産党員としての組織生活や闘争経歴などすべての点で金日成をはるかに凌駕する。」であるのに、党でも政府でも、金が主で、朴は副というポジションに甘んじさせられた。もちろん、金日成はソ連軍の傀儡としてそのポジションを占めていただけだが後にそのポジションを利用して他の指導者を順次粛清していき独裁を完成していく。
麗羅が朴憲永の第一の間違いとして記すのは、下記だ。
「1946年の大邱人民抗争以来散発的な抵抗運動を展開しながらも、1947年の夏において、全面的な革命戦争の開始を躊躇したことである。その時点では、南における南労党の組織率は60パーセントを越えていた。朴憲永が蜂起を命じたら、アメリカ軍が駐留する二、三の都市を除いて南の大部分は数日のうちに制圧できたことは間違いない。」(P195)
そして、
「第二の間違いは、朴憲永は絶対に北に行くべきではなかったことだ。
彼が北へ行ったのは1947年の春で、左翼陣営にたいするアメリカ軍政庁の弾圧がきびしくなったために一身の安全をはかってのことだといわれているが(略)。
彼の北行きは、軍人でいえば戦線離脱であり、危険水域にさしかかった船の船長が、船と船員を見捨てて逃げ出したに等しい。(略)
彼は南を離れていたから、その夏の一斉蜂起の絶好の機会を逸したのだ。
そして、朴が越北したのちの南労党は司令官を失った軍隊にひとしく、地方幹部たちは局部的に果敢に闘争を展開したが、全体的には頽勢の一途をたどった。
一時は成人男子の6割以上を獲得した南労党(左翼陣営)の地上組織は、1947年8月から翌48年の3月までにほとんど壊滅して地下組織のみが細々と存続する状態に追いこまれ、頼みとするゲリラ闘争も相次ぐ討伐と隊員の脱落によって日を追って弱体化するばかりだった。」
それでも「南北を統一するには南に人民革命を起こして共産党が権力を把握したのちに、北の共産政府と合併する」という発想を捨てなかった、朴憲永は。
それに対して金日成は「北の人民軍を投入して南進統一する」発想を捨てず、朝鮮戦争を起こす。全面武力対立は金日成の目論見に反し米軍の全面反攻をもたらし、結局戦争は勝てなかった。金日成は戦争の責任を取ることもなく、権力を維持し続けた。
(ここからは野原の感想だが)ソ連監視下の平壌という狭い場所での権力闘争というゲームにおいて、朴憲永は金日成よりずっと下手だった。そして70年後も金日成の孫が自己権力を維持し続けていることを私たちは深く気づくべきである。
つまり、朴憲永の共産主義、ソ連、そうした理想への期待が、リアリストであるべき政治家の目を狂わせ敗北に至った。そしてその問題は私たちにおいてもまだ終わっていないのだ。