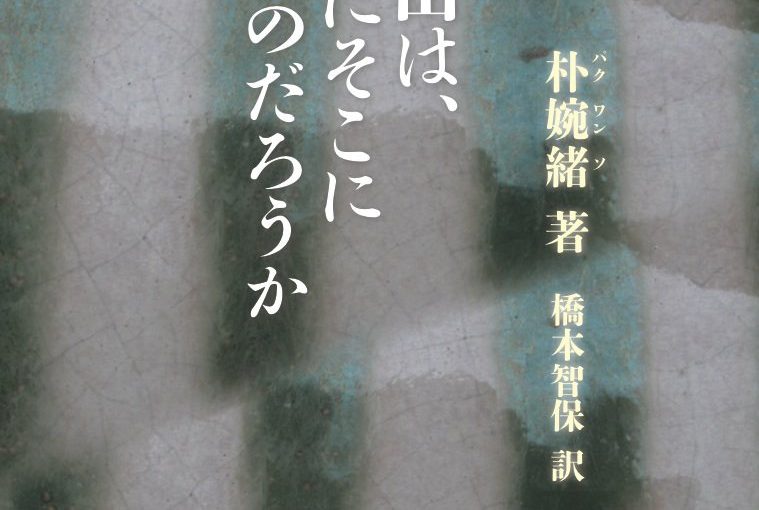宮廷女官チャングムの誓い、54話もある長いドラマ。見ました。2003年の作品、脚本:キム・ヨンヒョン 演出:イ・ビョンフン。
中宗(チュンジョン 1506年 – 1544年)時代ごろの朝鮮の王宮を舞台にしている。
この時代に限らず朝鮮王朝時代は、支配階級のあいだに儒教が浸透し、女性のさまざまな活動が非常に制限されていた時代である。
そのなかで、唯一王の主治医となり「大長今(偉大なるチャングム)」として歴史書に名前が残っている女性がチャングムなのだ。https://kankoku-drama.com/historia_topic/id=12001
といっても、名前以外ほとんど資料がない。ありえたかもしれない一人の女性の闘いの一生を、作家は美しく描き出す事に成功した。(もっとのびのびと活躍したかったという500年間の女性の夢を、この一人の人物に集約させるように作られたキャラクターだとも言える。)
王宮には多くの女性たちがいた。王宮に入る女性は賤民や早くに両親を亡くしたものが多かったとされる。
https://zero-kihiroblog.com/trivia/nyokan/#index_id3
重要な仕事をさせられることもある一方、都合が悪くなればいつでも殺すことができるそうした存在だったのだろう。男と違い最初から権利を持たない存在だと位置づけておけば、とても使いやすい。
彼女たちは、幼くして王宮に連れてこられて以来、王宮の外に出ることも許されず、男性と付き合うことも許されず、子を持つこともできず寂しく死くしかない。王宮という人工的な世界でしか生きられない、死ぬとき以外王宮を出ることができない女性たち。
ただ、ドラマでは女性たちが色鮮やかな料理を作っている日常が続き、基調はおだやかなので安心して見続けることができる。
このドラマのテーマは、ハン尚宮とチャングムとの世代を越えたシスターフッドだろう。その背後には、パク・ミョンイ(チャングムの母)とハン尚宮との友情が、ミョンイの水剌間(スラッカン、宮中の台所)からの追放、毒殺(未遂)により壊されるという関係がある。ミョンイを追放したのはチェ尚宮の一族。彼らがこの長いドラマで権力側としてずっと悪役をつとめる。チャングムを育て見守ってくれたハン尚宮も途中で追放され、その途上で死んでいく。
ドラマの最後では、チェ尚宮一派の罪は暴かれ裁かれることになる。ところが、チェ尚宮一人だけは逃げ出し、宮中の外にまで出ていく。どこに行くのかと思えば、なんと(自分が殺した)ミョンイの墓である。チェ尚宮とミョンイは、幼い頃から水剌間の見習いとして育った親友だったのだ。チェ尚宮は家と権力を守るために手を汚すことを厭わず生きてきた自分を、否定し反省するだけの力も持てず、幼年期に退行する。そして松の木の枝にかかったリボンを取ろうとして(あるいはそういう幻影を見て)崖から落ちて死んでしまう。
クミョンはチェ尚宮の姪であり、水剌間の最高尚宮としての地位を引き継いだ。しかし幼いころはやはりチャングムとの友情があったのだ。
女官たちは幼少期から世間から隔絶した閉鎖空間、理不尽な権力関係に振り回される奇妙な空間に生き続けなければならず、しかも出口はない。このような長く続く世界で営まれた、回帰するシスターフッドというものが、このドラマのテーマである。
チャングムは最初后と、次に王からも信頼を得ることが出来、それによって復讐を遂げることができた。后も王も最高権力という立場にありながら、誰にもこころを許すことができずひどく孤独である。それがチャングムを急に評価するようになった原因でもある。后はチャングムにこころを許すあまり、対立する王子(中宮)の命を縮めることを命じる。后との関係を断たない限り、悪に手を染めるしかない立場に置かれる。(宮中の権力関係というのは苛酷であり、ほとんど殺さなければ殺されるといった関係なのだ。)この直後、チャングムは一時的に水剌間の最高尚宮にもなる。この二つのエピソードが示しているのは、母を殺したチェ尚宮、このドラマの敵役とチャングムとの同一性である。存在様式としての同一性と言いたい。最高尚宮としてのチャングムの姿はそのことをビジュアル的にも明らかにしている。
王宮という閉ざされた空間で繰り返されるのは、自己が生き延びるために他者を排除する悪に加担せざるをえないというつまらない反復である。
それに対して、チャングムが貫いているのは、どんな場合にもその人を害することになる食事(あるいは医療)は出さないという倫理である。罪なくして死に追いやられた母とハン尚宮の復讐をするためにチャングムは王宮に帰ってきた、そして自ら悪行をすることなくして復讐を果たすという、不可能だと思われていたことをやり遂げた。
しかし、振り返ってみれば、幼い頃宮中に来てから死に至るまでチェ尚宮の生はミョンイの生の反復であり、同じようにチャングムの生を反復しているのがクミョンである。女官として同じような外見と人生から外れることができない彼女たちには、差異よりは反復が大きく感じられる。
朝鮮王朝で何の積極性も主体性もなく抑圧されたばかりで数百年過ごした女性たち。そんなことはないと証したのがチャングムであり、そしてすべての女たちも、また少しづつはチャングムであったのだ。
なお、「シスターフッドとは、男性優位の社会を変えるため、階級や人種、性的嗜好を超えて女性同士が連帯すること」とされる。https://www.tjapan.jp/entertainment/17528215
しかし、全く同じ空間、権力関係のなかで何十年もすごした女どうしの友情/憎悪、に対してもシスターフッドという言葉を使うことも許されるのではないか。
朝鮮王朝期には男性優位の社会を変えるといった問題意識はまったくなかった。王宮という閉じられた世界では、どのように新しいことをやろうとしてもそれは挫折し出発点に戻るしかない。王宮の女性たちはすべて同じ立場に置かれており、そのことを良く知っている。その必然性を裏切る〈一瞬の夢〉としてチャングムは現れた。チャングムを見つめる女官たちの視線には、反復するシスターフッドが、逆説的に表れている。