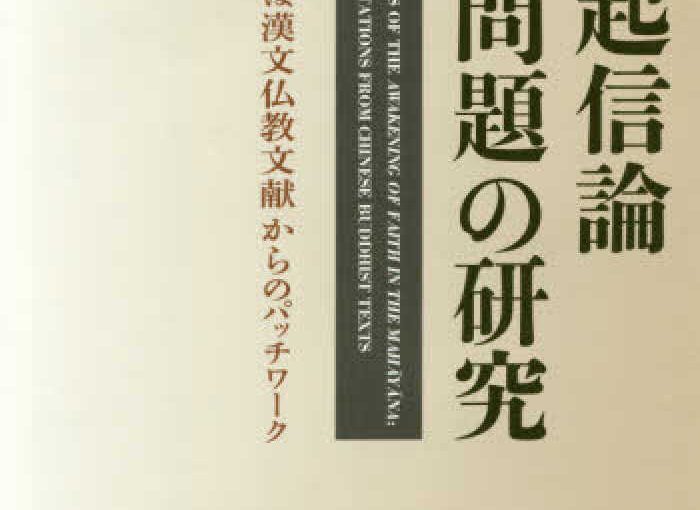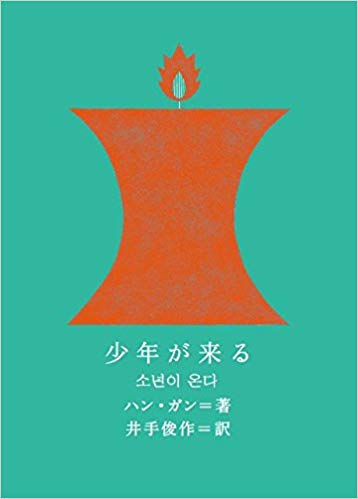河村発言などによって「表現の不自由展・その後」が中止に追い込まれて、以降いろんな考察がでています。
小田原のどか氏による長い文章を読んでみます。「私たちは何を学べるのか?「表現の不自由展・その後」」
問題の核心を、「中止に至った問題の諸相を単純に腑分けすれば、政府高官からの介入、市民による抗議、そして脅迫があると考えられる。」
「文化芸術基本法の理念に反する行為である。脅迫や、政治家による公金を理由にした介入などの暴力を決して許してはならない。しかし、河村たかし名古屋市長の来歴を見れば、《平和の少女像》を批判する発言が出てくることはごく「当然」なのである(*1)」
ととらえる。
☆ 河村名古屋市長は、政府高官ではない。
なぜそういう誤記をするのか。タブー意識が働いているのではないか?
☆ 河村市長が、慰安婦像を「どう考えても日本人の、国民の心を踏みにじるもの」として批判し、この発言を日本人の少なくない部分が肯定的に受け入れた。これが今回の事態の核心だと思われる。
保障されなければならない「表現の自由」なるものが侵された、と捉えるのは浅いのではないか?
行政の長に過ぎない河村氏が、「日本人の、国民の心」というのものに介入発言をしそれにかなり成功していること、これに対して、アートの人も「心」というフィールドにおいて、真正面から敵対していくことが必要だと思われる。
☆ 「《平和の少女像》に反感を抱く人々のなかには、像の建立と、政府間の慰安婦問題には直接的関係がないということを知らない人も多いのではないかと想像する。この構図を周知させることが、像への悪感情を和らげることにもつながるだろう。」
反感を抱く人は存在する。で反感に権利を認めるべきか。
私は権利はないと考える。そもそも「少女像への反感」は2015年安倍首相側からは「大きな汚点」と考えられた「謝罪」に対して、その謝罪の意味をごまかすために「大使館前少女像」に怒ってみせた、という政治的策動に端を発したものである。今回、河村市長が強い口調で断言的に怒ってみせた効果として、《平和の少女像》への反感が事後的に生まれたのである。
それに対して、「反感」というものを自然化し、あるいは「現状の展示場を見る限り、表現の問題ではなく政治の問題としてのみ焦点化されている印象が非常に強い」として作家〜展示者側の問題が気になってしまうのは、「少女像」をめぐる感受性の政治学の激動を完全にとらえそこなっていると思う。
そもそも、「少女像」が作られたのはソウル水曜デモが何十年も継続していることへの驚きからである。水曜デモは70年以上前の日本軍の暴虐に抗議しているのではない。河村発言を受け入れるような現代日本人の半端な被害者意識によって、自分たちの告発が聞き届けられないことへの抗議である。
☆「たとえ歴史認識のすりあわせが難しくとも、」:慰安婦問題については安倍氏も「当時の軍の関与の下に,多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題であり,かかる観点から,日本政府は責任を痛感している。」と認めている。この認識からは、少女像が「どう考えても日本人の、国民の心を踏みにじるもの」である、はでてこない。少なくとも私にはその理路が分からない。だから私はなん人もの人にそれを聞いて回ったが誰からも答えはなかった。
河村氏がいったいどのような歴史認識に立脚しているのか?それは小田原氏は確認している。「2007年、自民、民主両党の靖国派国会議員らが中心となり、米紙ワシントン・ポストへの意見広告「THE FACTS」を出した」それを読んだようだ。
河村氏はこうした認識に基づき、「どう考えても日本人の、国民の心を踏みにじるもの」という感受性領域に対する傲慢な介入をした。
☆ 「そしてまた、より普遍的に考えれば、女性の人権が踏みにじられた過去を真摯に省みて、二度と繰り返さないという点では対立を超えることができるはずだ。」
ここにあるのは「政治性」というものに囚われることは、対立の激化につながる。「政治性」というものを脱却していけば「対立を超えることができるはずだ」といった構図、であろう。
現在の問題ではなく過去の問題だと捉えれば、「対立を超えることができるはずだ」と考えたい。
しかし、水曜デモが27年間、ある意味で無駄に積み重ねられざるをえなかったのは、つまりキム・ソギョン/キム・ウンソンが連帯を捧げようとしたものは、過去の問題ではない。「THE FACTS」のような歴史修正主義言説を生み出してしまう心の弱さという現在性に対する戦いである、と私は理解する。
河村氏たちというものは現在、日本において膨大な存在感として存在している。したがって、「愚か者」「テロリスト予備軍」と断じるだけでは終わらせることはできない。
河村氏たちすらも包括しうるような広大な慈悲といった立場に、究極的には到達すべきなのかもしれない。しかし、アートの立場は宗教の立場ではない。あえていうならば、27年間の河村発言に到る「歴史修正主義」発言の総体に憎悪でもって肉薄することこそが、想像力の戦いとしてなされるべきことであろう。
☆ 「憎悪」「対立」「正義」といったものは、アートとは別の領域にあるべきものだ、という思い込みはアートの弱体化にしか繋がらない。
☆ 小田原氏は、広島、長崎の資料館での加害/被害展示のあり方についてなども、持続的に考えておられる。2つの原爆資料館、その「展示」が伝えるもの
☆ 小田原氏は、天皇が「一度おばあさん[元慰安婦]の手を握り云々」という、文喜相(ムン・ヒサン)韓国国会議長発言については、こう書いている。
これに対し日本政府は「不適切な部分がある」として謝罪と撤回を求めている。しかし政府は「不適切な部分」について、それが昭和天皇を戦争犯罪の主犯と呼んだことにあるのか、それとも上皇の謝罪を望んだことなのか、具体的には明らかにしていない。平成から令和に変わり「新しい時代」などとかまびすしいが、いったいどこに新しさなどあろうか。日韓のあいだには、変わらず深い溝が横たわっている。(北緯38度線の分断から見えるものとは何か?)
静かだが、言うべきことは言い切っている。
今回の文章の河村発言については、明らかにトーンが変わっている。