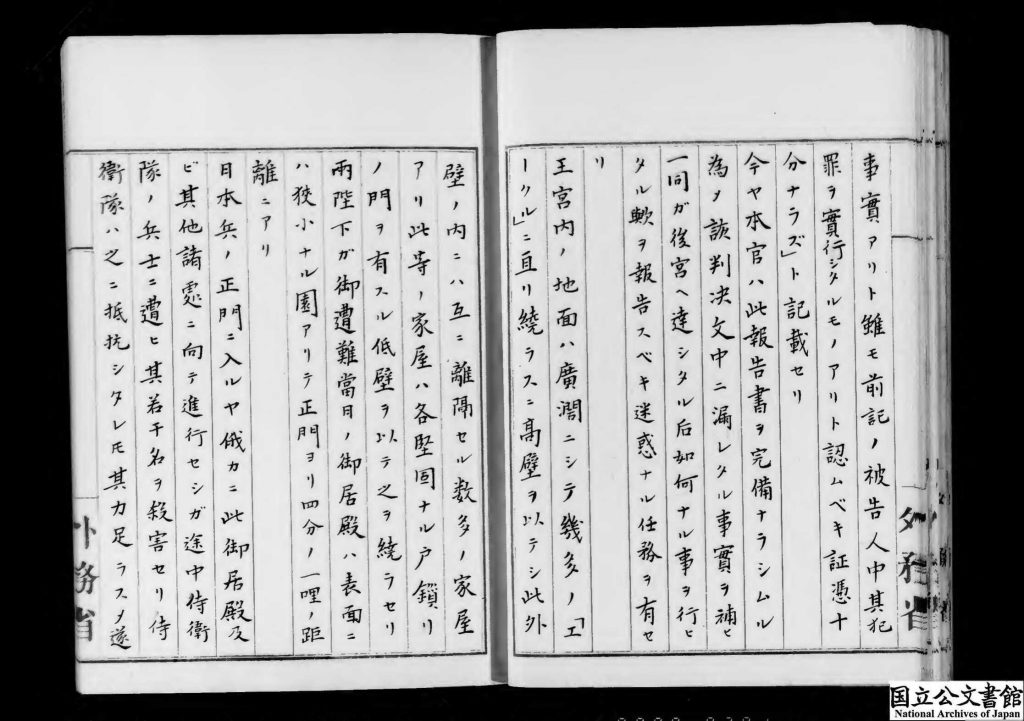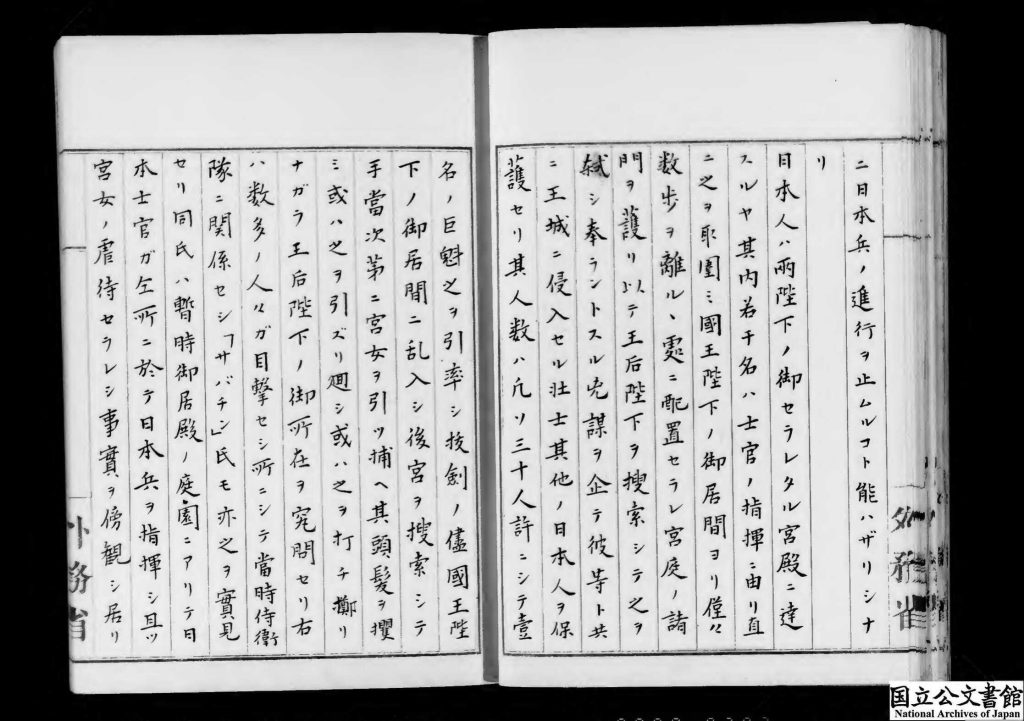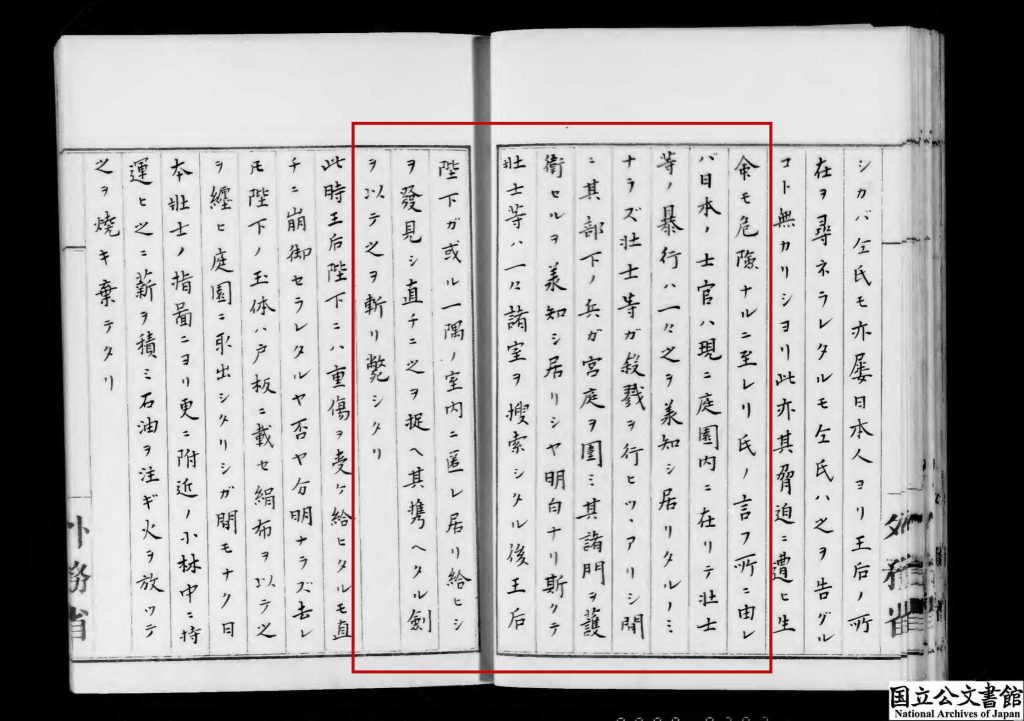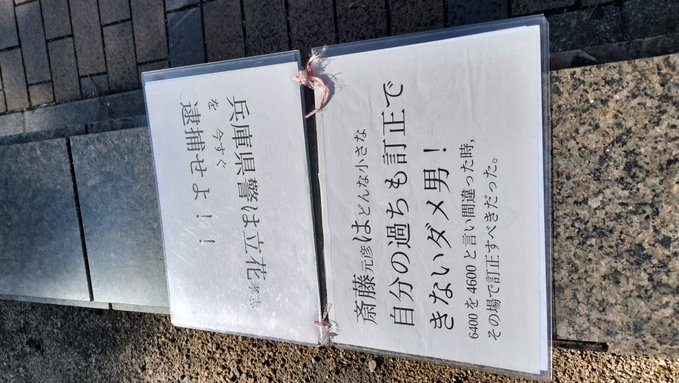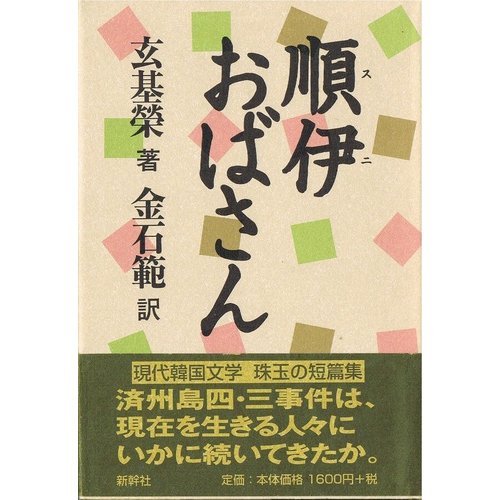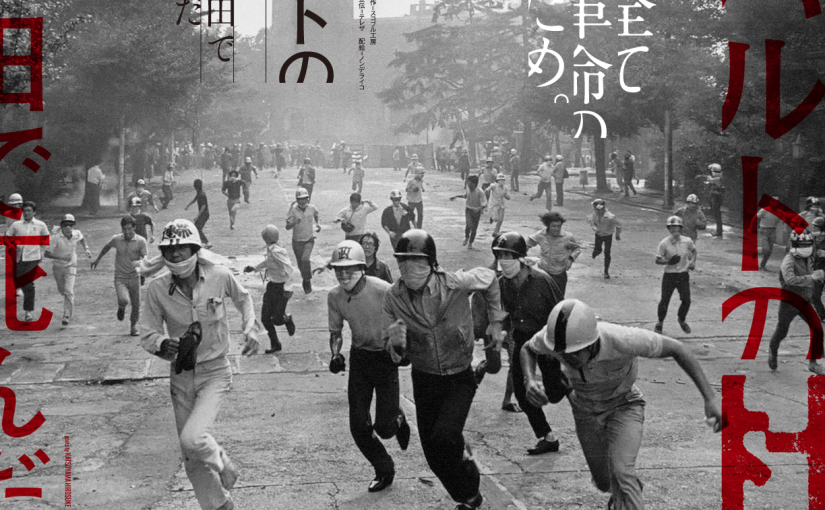「X団」顛末記 を読んで
(1)
『ゲバルトの杜』という映画を見た。この映画がよい映画だったのかどうか、良くわからない。なのでこの感想は書かない。当事者(登場人物)の一人、野崎泰志さんが書いた長い回想が、インターネットにある。「「X団」顛末記―樋田毅著『彼は早稲田で死んだ』に寄せてー 「正しく公正で確かな力(村上春樹)」は私達の言葉にあったかー」https://ynozaki2024.hatenablog.com/entry/2024/05/09/231009 。
(https://ynozaki2024.hatenablog.com には他の記事も精力的に追加されている。)
広義の全共闘の時代の青春と正義を描いたドキュメントとして(かならずしも読みやすくはないが)稀有のものだと思う。以下に感想を書いてみたい。
「1972年11月8日の夜、早稲田大学文学部キャンパスの学生自治会室で、当時二年生の川口大三郎君(20歳)が学生自治会の革マル派によってリンチ殺害された。」
それに怒った早稲田数万の学生は立ち上がった。学生たちの目的を二つに整理することができる。革マルによる暴力支配を終わらせることと「自治会再建運動」である。
川口くんの属した「第一文学部の学生は先頭を切って学生大会を開催し、その自治会(革マル系)をリコールして臨時執行部を樹立した。その委員長が『彼は早稲田で死んだ』を上梓した樋田毅氏、副委員長が私(野崎)だった。」
学生たちは、革マル派の暴力支配に抗しつつ運動を続けて行こうとする。ただし、学生たちのあいだにも思想傾向の違いがあった。当時の膨大な資料を再構成することにより野崎氏は、自分たちの思想(行動と不可分な)を、他の二つの潮流から区別していく。
「行動委員会とは、個々人の主体的な決意を基本とし“自立・創意・連合”の原則で進んでいく」そうしたもののようだ。わたしはその心意気に、50年前に出会っていたら同感しただろう。
そのとき、野崎氏たちの前にあった課題は明白だった。友人だった川口くんが殺された。それをなんとかしないといけない。復讐の情念に似ている。しかし革マル派への憎悪だけに収束してはいけない。また革マルを否定する党派(例えば中核)を志向してもいけない。(セクトを志向することは、自分だけで考えるという態度を捨てること、思想をセクト中央に委ねることを意味する。)自分が自分として生きることを模索するという青臭さを引き受けること、そのように野崎氏たちは出発した。
ただ〈行動委員会〉的なものは、野崎氏たちにとって次第に違和として現れる。この野崎氏たち(後にグレーヘルメットのx団として表れたもの)と〈行動委員会〉的なものとの差異は微妙なので、抽象的なものである言葉で捉えるのは難しい。1971年に大学に入学した、同世代である私には分かる気もするが。
ある種の大人たちからはそこに思想の根拠を置いてはいけないと嘲笑される即自的なものに、野崎氏たちは依拠する。クラスがそれだ。
「私は徹夜でクラス決議案を書いた。
11月10日金曜日は大学が休講措置をとった。それを知らず級友がいつも通り20数人集まった。クラス決議案を討議し一字一句修正した。私は後に引かない覚悟で、賛同の者の氏名を列挙すると言った。」
正確には、〈クラス討論〉という開かれた討論空間であるが、それは友情(なかま)という即自性の強い共同性でもあった。開かれた討論空間であるとは、世界を包括しうるということである。この楽しみと喜びにとらわれた野崎氏たちは、稀有なことだろうが膨大な暴力がうずまく大学のなかで、それらとは別の次元の〈クラス討論〉空間をかなり長いあいだ維持することができた。クラスとは大学の制度内の集団という平板な意味ではない。ひとつの世界に開かれた共同性であるのだ。そのとき交わされた討論が意味あるものであれば、それは数十年後にもためらうことなく再開することができる。出版〜映画化〜いくつかのブログ〜SNSと討論は再開されつつある!
『行動委員会とは、個々人の主体的な決意を基*とし“自立・創意・連合”の原則によって各人の、各クラスの闘いとエネルギーを能動的に機動的に結合してゆく連動体である。全てのクラス・サークルで行動委員会を創出し臨執を守り、臨執の闘いを実体的に保*し、共に闘いを進めてゆかねばならない。
何度でも云う。我々の闘いは生み出されたばかりである』x2-2
ここで定義された〈行動委員会〉は“自立・創意・連合”の原則(つまり開かれた討論空間)であり、またクラス・サークルというたまたまであった友人たちの即自性に依拠するという点で、野崎氏たちと同じである。
しかし、野崎氏は第1章すべてを費やして〈行動委員会〉的なものと自分たちの差異を確認しようとする。
〈行動委員会〉の原理は、「やりたい者がやりたい事をやる」という全共闘方式で、学生自治会の基盤としての民主的クラス活動とは異なる。」と野崎氏はいう。自分たちは自治会再建運動をやっているのだであり、全共闘方式とは違うというのである。
第一文学部学生自治会の9原則(野崎氏が書いた)というものがある。
- セクトの存在は認めるが、セクト主義的ひき回しは一切認めない
- 革マル派のセクト主義に対して、我々は大衆的な運動・団結をもって彼らの論理と組織を糾弾していくのであり又、そうでしかあり得ない
- 我々はセクトに所属している人間というだけで、その人の主張を無視してはならない。我々は具体的な事実、主張の下に初めて批判を行なっていくべきである
- 意見の違いは大衆的な討論の場で克服していく努力をする
- 我々の運動の質・形態・思想は常に運動の中から生み出され大衆的に確認していかねばならない(以下略)
革マル派糾弾を掲げつつ、(そこに属していたとしても)その人の主張を無視してはならない、と主張しており、討論空間の権威を誇っていると読める。
このように討論を大きく重視する場合、現在考えてみると問題点を指摘することもできるだろう。
発言できないもの、障害者、幼児、病者などなどサバルタンの存在をどう見るかという問題。
また、運動、大衆的という言葉の圏域に立つなら、村上春樹や文学、孤立、死といった問題を包括できないのではという問いもある。
現実的問題としては、全共闘体験者(66〜70年入学者?)がすでに直面していた卒業/就職問題にまったく触れることができていないという問題がある。(松下昇の祝福としての0点は、たしかに一つの回答ではあった。東アジア反日武装戦線の反日も。)(なお、反日といってもテロとは限らない、単に肉体労働者としてその日ぐらしをする、桐島聡のように、もりっぱな反日だろう。)
〈行動委員会〉的なものと野崎氏たちの分岐は、具体的には、一文行動委連合(準)略称LACなどと臨時執行委員会との分岐である。つまり「行動委員会とは第二次早大闘争の生き残りの世代の3・4年生中心に立ち上がった活動家の集合であり、同時に革マル派と敵対していた政治党派の活動家(手書きビラの書体と語彙で当時は分かった)の寄り合い世帯で」あり、臨時執行委員会とは1,2年生だった。
「3・4年生で行動委に結集した学生はクラス活動の基盤をほぼ持っていないという背景があった。語学クラス単位で行動した1・2年生はクラス討論を基礎に自治会再建に取り組み自治委員をほとんど選出した。この自治委員選出率、一年73%、二年75%、三年39%、四年0%と云う数字にも、行動委員会が自治会再建に淡白で直接行動に傾き、1・2年生が自治会再建運動に重点を置いていた当初からの関係のねじれが見て取れる。」
自治委員選出率の極端な落差は、大学というもの(それをどう捉えるにしろ)への親和感を3,4年生はほとんど失っていたという問題があったのではないか?1,2年生はクラスの即自性に夢を託する余地があった。
実際、3年U氏と4年K氏はクラス自治委員として選出されなかったので、執行部からはずされた。
規約改正委員会(野崎氏たち?)の次のことばは美しい。
「各個人の自発性に根拠を置き、自由で豊富な人間関係を確かに、また持続的に組み上げていく努力を通じて、問題意識が(それは心のなかに不安として、痛みとしてある。)交流し、真実の共同的努力のうちに、自立的な人間へと相互に高めあっていくことが、自治の内実ではないだろうか。
〈行動委員会〉的なものと野崎氏たちの分岐を、表現された文言のうちに伺うことは困難だ、とも言える。それはむしろ彼らの存在様式(1,2年生はモラトリアムを許されていた)から来ていた。
民青系の学生が立候補してもよいか?という問題があった。9原則の「3. 我々はセクトに所属している人間というだけで、その人の主張を無視してはならない。」からは、許容するという考えになる。自治会再建という目的のためには、民青も受け入れるとする。
この50年の経過を見ると、9原則派の方が正しかっただろうと感じる。血みどろで対立してしまえば、人間的にはその後の和解は難しい。しかし、ある具体的局面で敵に対峙するとき第三勢力として日本共産党や中核が居れば、共闘の可能性に開かれているべきだろう。自分の思想を守るためにそこで孤立を選ぶというのは間違いだろう。大事なことは自分の思想ではない。開かれてあることである。巻き込まれて自分をなくしてしまうなら、それはその思想が弱かったのでありしかたがない。(しかし、逆に相手にも同化を求めるなという態度は必要。)
「団交実行委員会は行動委員会系の学生が次に形成した運動体で、各学部にも作られ最後に全学団交実行委員会となる。これが後の1973年5月8日の総長拉致・団交を実行し」た。
行動委員会派は「自己否定・自己変革を通した主体性の確立を闘争の主眼とする」ということのようだ。
「地道なクラス討論を積み上げて、自治会の在り方や試験への対応や新規約など、ゼロから大衆的論議を尽くして自治会を創設していく」というクラスのニーズに、自治会再建派は立脚する。しかしそれは学費の支払いによるブルジョア的権利のなかでの友情(関係性)に、それを越えようとする不可能な夢をむりやり乗せようとしたものに過ぎないともいえる。そういう意味で、論理的・倫理的には「自己否定・自己変革」という立場の方が正しいようにも思える。
しかし考えてみればたった2年間とはいえ、1年2年制は「クラス」という実存を生きることができるのであり、そうした学生による自治組織を希求するのは当然である。そして大学側との度重なる交渉の結果「各学部の自治会承認はその一歩手前まで行っていたのである。」
したがって、5月8日の総長拉致・団交、つまり「旧世代の全共闘の好きなことを勝手にやると云う惰性」による運動(団交実行委=行動委員会派)が、「自治会再建と云う地道な作業を積み上げていた圧倒的多数の学生の望みを断ち切る事になる」。
これこそが、行動委員会派と野崎氏たち自治会再建派との決定的分岐となってしまった。
(2)
次の分岐は、「武装」をめぐってのものだ。
この映画の原作とも言える本を書いた樋田毅氏は一貫して非武装派である。それに対し、野崎氏たちx団派は、最終的に鉄パイプによる武装を選択し、武闘訓練まで行った。
これについて、野崎氏は次のように書く。73.6.17日。
「 個体としての己の生を誰も代行的に他人に生きてもらうことがありえないように、個体としての己の意思・思想・感性の表現を己のこととして貫き、決して疎外させ代行させることなく、自らの言葉を以って語っていく、——これが最低限の原則ではないのか。とすれば、己の表現を物理力をもって奪われている時に、己のゲヴァルト空間を確保し抵抗すること以外にどんな道があろうか。
己のことばを表現を己から疎外させ誰かに代行させてはならない。同じ意味で、己の自衛権をゲヴァルトを己の肉体から疎外させ誰かに代行させてはならない。セクト主義的引き廻しを許さないと言う観点から言っても、種々のセクトやWACなどのゲヴァルト代行は、運動の自立をさまたげるだけに留まらず、思想的にも運動の敗北を決定的にするであろう。」
この文章は魅力的である。自分で考えて言葉を発するのではなくセクトの思想・表現を(疑うことがなくなるまでに)自分のものとして語ってしまうこと、そのようなあり方を批判することこそがセクト批判であろう。であるとすれば、己の自衛権についてもそれを他人(他のセクトやWACなど)に任せてお願いするのではなく、自己のゲヴァルト行使として自己の行為とするべきだ、という主張。
革マルによる暴力的妨害をはねのけないと大学構内に入ることすらできないという事態において、防衛を他のセクトやWACにお願いするということがいままで成されていた。それを代行主義として批判し、自ら防衛すると言っている。
ただ、ヘルメット・竹竿までは身につけることができても、鉄パイプという凶器を持つことについては覚悟がいったであろう。
「川口君の虐殺事件を機に、『反暴力』を掲げてこれまで一緒に闘ってきた同じ二年生の仲間たちが、防衛のためとはいえ、『武装』することを決めたのだ。療養中だった私は、その経緯を後になって知り、激しいショックを受けた。」(樋田毅『彼は早稲田で死んだ』、p148、166)(療養の原因は革マルの暴行。)
革マルの暴力に対抗するために、対抗暴力としての武装は許されるか?「テロ・リンチはせず大衆の目前での公然たる暴力であること、目的が確認された暴力であること等」議論がなされた。大学に入り、学内で集会するために、防衛のための武装が必要となったのだ。
わたしたちが非暴力で生きていますとのほほんと信じているとすれば、それは自らを覆っている国家権力の暴力を無自覚に肯定しそれに気づいていないということであろう。それが通用しない例外的状況(この早稲田の状況がそうだが)においては新しい基準が必要になるだろう。
非暴力を貫くという樋田氏の思想は正しいだろうか。「人権として正当な抵抗権としての自衛行為」を認めることができない思想だ、と野崎氏は批判する。
口先だけの非暴力主義が日本では蔓延している。そのような非暴力主義の蔓延はバリケードやストライキにも反対する空気を作っていって、社会運動の衰弱につながると言えるだろう。
刑法的にも正当防衛の可能性はある。(ただし事前に鉄パイプを用意していた場合は、とっさにそこにあった何かを手にした場合より認められる可能性は低い)。防衛の意志をもって鉄パイプを持つことはあってもよいと私は考える。
武装に反対する理由としてよく言われるのは、暴力は必ず相互エスカレートするということだ。早稲田の72年11.8から、73年9月までの経過はまさに暴力のエスカレーションであった。但し、革マルやそれに対抗した中核、青解などセクト(政治党派)の暴力と、個人の身体を基盤にしたx団の暴力はやはり違うものだろう。x団の暴力は防衛というレベルを逸脱しなかった。
もうひとつ別の暴力については、引用だけしておく。
「ただし、X団の別動女性部隊「ウンコ軍団」はスロープを突撃して上がってくる革マル精鋭部隊約50名に対して、用意していたビニール袋のウンコ爆弾を2階の窓から雨霰と投げつけた。命中したのであろう、彼女らは女子トイレまで追われてそのドアーを鉄パイプでボロボロにされる恐怖を味わった。」
「一文学生自治会憲章「九原則」では、一言で言えば自律しか書いてない。非暴力とは書いてない。自律が侵されそうな局面で自衛的実力行使を一文学生は幾度も行った。更に必要に迫られれば自衛武装的実力行使に及ぶのは自然であろう。自分の人権は自分で守るしかない。一人一人がそう思えば大きな力になる。」が野崎氏の結論である。
「しかし、新自治会の防衛を自衛武装で試みたX団と二連協の”ICHIBUN 80”も、確かに無知で無力であったが、確かな敗北の痛みだけは手元に残った。」と最後に誇らしげに書きつける。
52年前に何があったか以上に、仲間との関係を回復し歴史を復活させるHPを作り上げるなどを仲間とともに行ってきた最近の営為によってもこの誇りは支えられているであろう。(19721108の頁)
暴力学生として唾棄されるだけの存在だという評価に、抗しうる自己史を書き留めることができた人は少ない。反革マルの闘いには真実があったし、それは表現されるべきだった。
野崎さんたちの苦闘と勇気にこころからの敬意を表したい。
(なお、早稲田大学と何の関わりもない私がなぜこの文章を自分に引きつけて読めたか。私は川口くん、野崎くんと同時である1971年4月に京大法学部に入学した。入学当初のクラス討論の空気を久しぶりに思い出してみると、そこには早稲田と同質のものがあったように思えたからだ。わたしたちは平和的に4年間を過ごすことができ卒業していった。「ブント系(赤ヘル)の全学支配のなか」と言えるだろう。悲惨な事件も時折あったようだが、あまりよく知らないままとおり過ぎていった。(民青とは勢力拮抗していた。)当時、竹本処分粉砕闘争や三里塚闘争などあったが参加せず、もっぱら本を読んでいただけだった。ただこの社会を否定・変革しなければならないという気分だけは100%持っており、従って卒業後どう生きればよいか分からなかった。)
参考:膨大な資料をまとめたサイトが二つある。わたしはまだ見れていません。
☆ (19721108の頁)
川口大三郎リンチ殺害事件の全貌 というサイト。野崎さんや旧クラスメートなどが作った時系列重視の詳細なもの。
☆ https://www.asahi-net.or.jp/~ir8h-st/kawaguchitsuitou.htm
川口大三郎君追悼資料室 瀬戸宏作成・管理
追記:
野崎さんのブログは最近旺盛に更新されているが、そのなかでどうしても引用したい部分が下記だ。
「https://ynozaki2024.hatenablog.com/entry/2024/05/17/214016
パレスチナに連帯して5月1日に本部キャンパス・大隈銅像前で約200人を集めてスタンディングデモ・集会をやった現役学生に言及し、激励し、過去の歴史に学んで欲しいと締め括ったのは、私だけだった。多分、それをやった諸君の中の20人ほどが見に来ていたと思ったので。歴史はバトンタッチされた。
その「スイカ同盟」の集会は、早稲田大学において、おそらく私達が1973年7月に最後の学生集会をやって以来の51年ぶりの、党派によらない、学生による自発的な政治集会だと思う。見事な演説であった。」
私たちが必死で形成してきたはずの平和のための国際秩序(国際法)のなかでその最も有力な暴力である米軍の支援の下で、ジェノサイドが行われている。私たちは抗議の声を上げることができるが、大きな不可能性の下にいる。