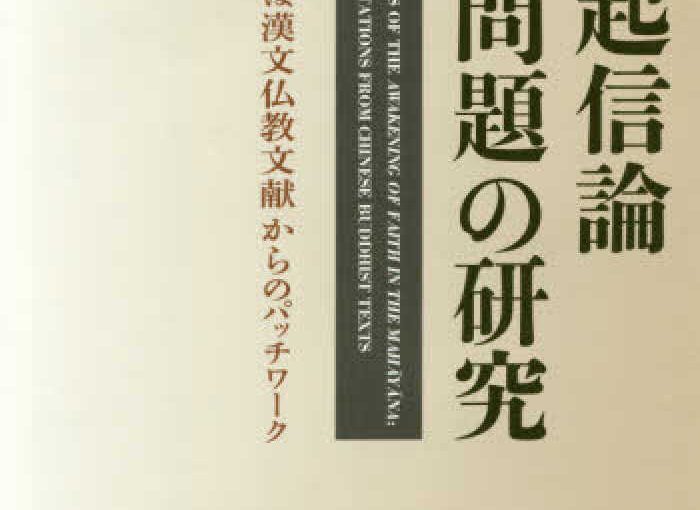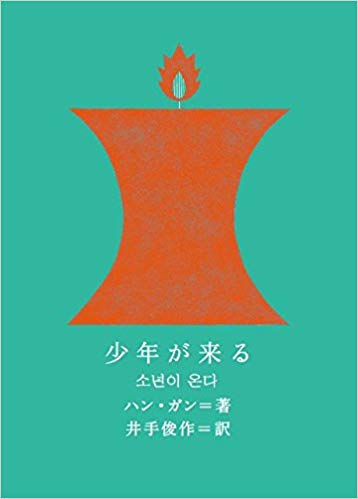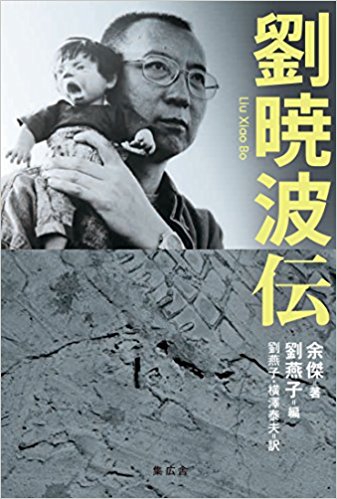7月ソウルへ、4日ほど行った。帰ってきて、徴用工問題からホワイト国除外問題、韓国側の反応や韓国からの旅行者が激減してしまったこと、あいちトリエンナーレでの「慰安婦像」に対する河村名古屋市長発言など、日本人の韓国認識の根幹に関わる問題が起こり、日韓関係は最悪となっています。この間わたしも少しだけ韓国について勉強しました。今まで不勉強だったことに今更ながら気づいた、わけですね。
1895年日清戦争において日本は短期間の戦いで、3億円以上の賠償金を獲得しました。これは、日本の大国化の途中の最も輝かしいできごとでした。主人公は外相陸奥宗光。「力ある者が何でもできるのは、帝国主義時代のならいである」、それを「冷静、現実的」にやりとげた「陸奥外交」こそ帝国主義の真髄である、と岡崎久彦は書いています。(1)
1894年東学の乱がおこると、「清国は朝鮮政府の要請を受けて出兵するとともに、天津条約に従ってこれを日本に通知し、日本もこれに対抗して出兵した。農民軍はこれをみて急ぎ朝鮮政府と和解したが、日清両国は朝鮮の内政改革をめぐって対立を深め、交戦状態に入った。」と山川出版社の『詳説日本史』には書いてあります。
戦争を始めるためには大義名分が要ります。「この上戦争の〈名〉はいかが相い成り候や、日本より無理に差し迫り、〈無名〉の戦争と相い成らざるよう祈る」と明治天皇側近も心配していました。(2)
「1876年江華条約一条に「朝鮮国は自主の邦にして」とある。現在朝鮮に清朝の軍隊が居るのは条約違反。撤兵要求しそれに応じないときは日本が代わって戦う。」というのが陸奥が考えた戦争の大義でした。
しかしその為には朝鮮政府から日本政府が「清軍駆逐」の依頼をもらう必要があります。しかし朝鮮王はださない。ではどうするか?
すでに1894.6.2日本軍は仁川に上陸していました。陸奥外相以下日本の総力をあげて、ソウルの朝鮮軍を一掃する計画が作られ、実行されました。
その核心部分は、王宮占拠、国王の捕獲、大院君を担ぎ出し日本の傀儡とすることです。
1894.7.23の王宮占拠の詳細を、金重明「物語朝鮮王朝の滅亡」という本から転記してみます。
漢城の日本軍は、周到な準備の末七月二十三日深夜、朝鮮の王宮、景福宮を取り囲み、一隊を王宮内に突入させた。
まず工兵隊が迎秋門の爆破を試みるが、爆薬が不足してうまくいかない。斧で打ち破ろうとするがこれも失敗する。最後は何人かの兵に塀を乗り越えさせ、内外よりのこぎりでかんぬきを裁断して、門を破った。この作業に手間取ったため、迎秋門突入は午前五時頃となってしまった。
王宮内に突入した日本軍は国王を擒(とりこ)とするため、ただちに捜索を開始する。
当時王宮侍衛隊は精兵といわれていた平壌の兵五百から編制されていた。王宮侍衛隊は四倍以上の日本軍に対し果敢に抵抗した。銃撃戦は数時間続き、双方に死傷者が出た。しかし衆寡敵せず、次第に侍衛隊は北方へ追い詰められていく。その間、日本軍の一隊が雍和門(ようわもん)内にいた国王を擒にしてしまう。
そしてついに、王から侍衛隊に、それ以上の抵抗はやめるようにとの命令が下るのである。王命に逆らうわけにはいかない。兵たちは悲憤律慨しながら、北方へ逃亡する。
日本軍はただちに、王宮と漢城内の朝鮮軍の武装解除にのりだす。分捕った武器は、大砲三十門、機関砲八門、小銃三千挺、雑武器無数であった。
さらに王宮に入った大鳥圭介は、兵を動員して王宮に所蔵されていた貴重な文化財をことごとく略奪し、仁川港から運び出してしまった。
国王を檎にした日本軍は、閔氏政権を打倒して、開化派を中心とした親日派政権を打ち立てるのである。(p149)
1894.8.20「日韓暫定合同条款」を日本は朝鮮に結ばせる。第4項が「本年7月23日王宮近傍において起こりたる両国兵員偶爾衝突事件は彼此共に之を追究せざるべし」です。真相を朝鮮側が口にしてはいけないと固く口止めしたのです。
日本政府は、事件当初からこの事件を、偶発的発砲が韓国側からあったので応戦した、という虚偽のストーリーにして、それだけを語り続けました。百年後の1994年に中塚が福島県立図書館で新資料を発掘するまでそのウソはくつがえされませんでした。普通の日本人は教えられていません。
しかし、日韓関係の原点とも言うべきこの暴虐な事件を知っておく必要はあるでしょう。日本国家の汚点であるからこそ。(2019.9.27)
(1)中塚明『現代日本の歴史認識』p215 から孫引。
(2)中塚明『現代日本の歴史認識』p199。