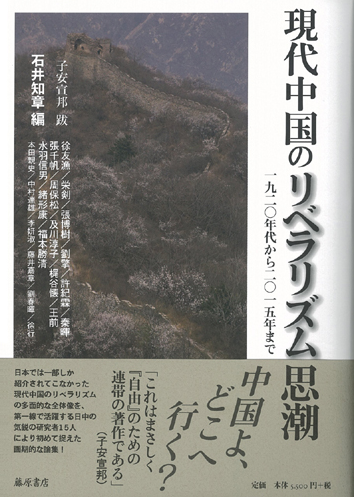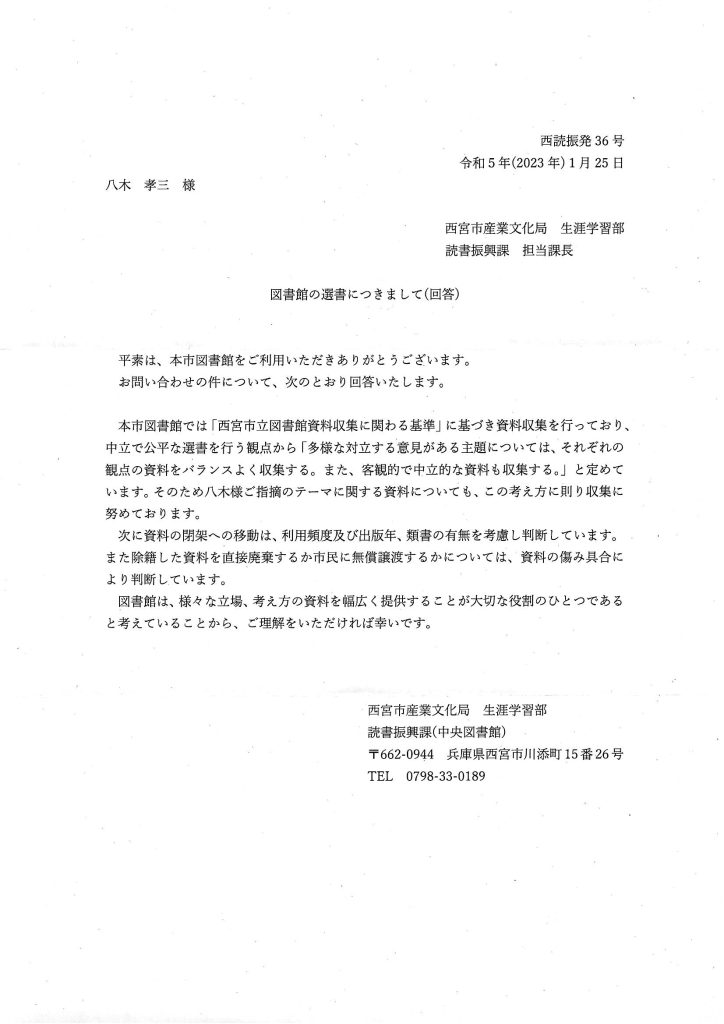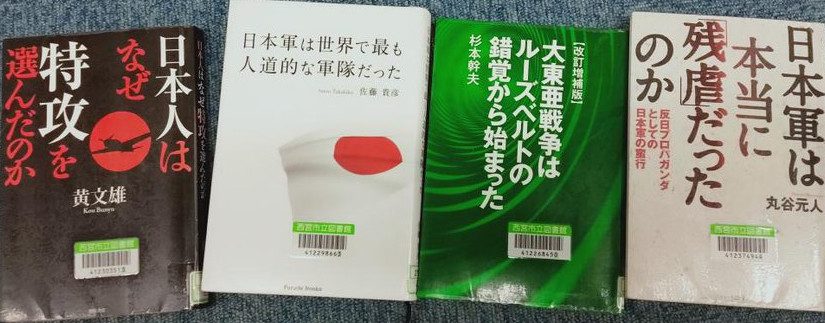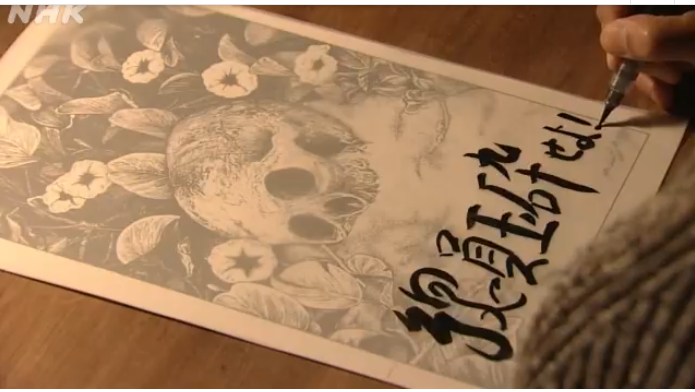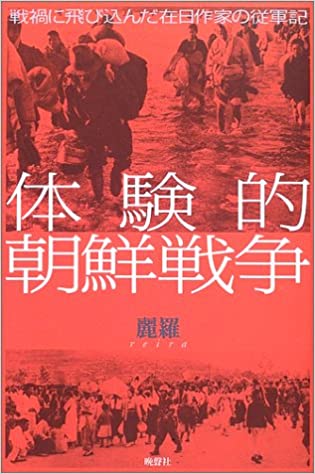図書館で、岩波書店の雑誌『思想』2023年2月号を手に取った。大黒弘慈「「あいだ」のフェティシズム」という奇妙な題の論文、ふと読み始めると、難しいがとても大切なことを言おうとしているようだと分かった。
フェティシズムという言葉は難しい。ギニア人が価値のなさそうなビーズに価値を見言い出したり、粗末な神像を拝んだり、というのがフェティシズム。ととりあえず理解する。
A :そのもの。例:木や紙で無造作に作った人形
〈A〉:フェティッシュ。おおきな神の予感。(信じてない人=近代的理性によって虚偽とされる)、という図式である。
フェティッシュ(物神)を否定しなければならないという常識をグレーバーは批判する。対象Aと主体Bとの安定した限定的関係がいつでも可能だしそれにたどり着けるという考え方に対する批判である。
われわれが創造的に生きようとするとき 物神は必ずしも悪いものではない。ただ危険な場合もある。p90 というふうに言っている。つまり、対象Aの本質、性質、質量などを私たちは客観的に捉え理解できるという前提に立つ時、それに対する例外としてフェティッシュがあるわけだ。
しかし私たちが生きているとき、ものAは慣れ親しんだものとか彼女が口にしていたものとか、そういうふうになんらかの情緒とともに存在している。であればそれは決して悪いものではないだろう。逆に、「ある種のフェティシズムをよすがにしてよりよい社会を築いていく」ことも可能なのではないか?それは「われわれがフェティシズムを作り出す行程について、理解しえない余地をあえて残すことによって可能になる」とグレーバーは言っている。p91
まあ、より正しい主体を求めていくことで、未来を獲得できるという考えを彼が取らないことは分かる。超越性への匂い(誘い)、ベクトルといったものを見出していくということだろうか。
でこの論文は、価値と権力の基礎とは何かを問い、その中で、新しい社会的現実を創造するためにフェティッシュが果たしうる可能性を探ろうとするものだ。
(第1章は「廣松渉、真木悠介、宇野弘蔵が、それぞれマルクスの「物神性論」を原理的なレベルでどのように読み替えていったのか」を追う章。ここではこの章に一切触れずに、残りの部分だけでの理解を書きます。)
第2章は「物神の消失/主体の埋没」となっている。
資本主義の現在は、対象Aの確実性が揺らいでいる時代である。例えば、サービス労働のような非物質的労働が優勢となっている。また、フェティッシュ崇拝は盛んになっている。「推し」消費の増大などに見られるように。
今日経済は非物質化している。貨幣の非物質化、ネットワーク上のbit列化が著しくすすんでいる。そしてまた、負債経済の下では、金融権力がわれわれに負債感情を植え付け、返済のために行動を画一化し、「正しい」生活規範へ順応させ、評価に縛られた空虚な活動に駆り立てられる。p108
疎外とは「人間の本質をモノに外化し、それによって逆に支配される事態」のことだった。であれば、ひとと人が対等に関わり感情を含めて交流する介護、保育などの仕事は「疎外されていない労働」という面も持つ。実際そこにやりがいを感じると語る人も多い。しかし実際にはそこには困窮(moneyの欠如)がある。
またひととひととの関係においては、〈対等性〉が重要である。サービスの受益者と供給者という格差の一方で、人対人としての〈対等性〉をどのように確保するか?その問いに開かれた関係を作っていくべきだろう。
ここで紹介されている今井里恵氏の論文は、今日の労働疎外の核心をこう語る。
「物を製作することにより他者との新たな関係を築き自己の物語を紡ぐような仕事の機会」が奪われていることだと。p108
彼女は仕事を「演技ゲーム」として、「他者とともに共同社会を能動的に構築していく作業は本来、根源的喜びである」と定義する。p109 個々人が自分の判断で不確実性への跳躍をして、自分の物語をつむぐことが「自由」である。
しかし、1970年代以降は、管理強化され、自由の感覚が奪われた「演技労働」に堕落した、と彼女は考えた。現在、わたしたちの労働は、不確実性への跳躍が一切奪われてしまっている。
マルクスは生産物があふれる豊かな社会になれば(さらに革命後)、人間の主体性や人と人との直接的関係が回復されるはずだと考えた。それは実現できていない。
ここで、「むしろフェティシズムを回復することによって、自由な主体は可能になり対称的な人間関係が可能になるのではないか?」と考えた人がいる。ラゥトールである。p110
物神を一掃し、事実の集積だけの世界を真実だと批判家は考える。しかしそれは結局同じことなのだとして、ラトゥールは「物神事実」 ということばを使う。
第3章は「理論と実践」と題されている。
実際はギニア人とポルトガル人のいずれも「超越性の像を作る」。そこには、構成された実在と内在的な超越、中途半端な物神事実どうしの対立があるだけであり、階層差はなく、いずれも物神崇拝者であるといえる。p112
物神が行為者を支配しているようにみえるが、実際は行為者が自分の力をその物に投影しているだけだ、と批判する。
そして、そのさらに背後には、多数の作用者、社会的群衆、諸関係、伝統というものがあり、力をあたえている。
批判的思想は、物神を一掃し、事実(A=Aである対象の群れ)だけが現実だとみなそうとする。
それに対し、ラゥトールの見方はもっとダイナミックであり、「自らの行為によって幾分か超過される」行為者を考えてみようと言う。
関係を、主体と客体、本質と本質としてスタティックに捉えるのではなく、行為と行為の関係として動的に捉えるべきだと言う。まあ、生きている上では客体自体をそのまま捉えることは困難であり、行為の中にしか現れないのはむしろありふれた体験になる。
ここで、パリ郊外の民族精神医学の治療現場という現場が出てくる。
精神医学なのに、個人の内面に注意を払い分析の中心にするということがない。そうではなく、彼らの崇拝物、祖国の祖父母、叔父、(サッカー)、そうしたものが複数の言語で語られる。患者は心理学的主体ではなく行為体になる。患者だけでなくその他多くの参加者たちがその過程で少しずつ変貌する。そのようにして、患者は治っていく。その人は患者としてではなく参加者のひとりとして、崇拝物を回復し主体となる。物神から解放された主体ではなく、「崇拝物をもつ準主体」である。p113
自由とは、完全な自由ではない。いくぶんか支配されることはむしろ不可欠なのだ。絶対的な自由などないといって諦めるのではなく、悪いつながりを良いつながりへと置き換える不断の営みが肝要だろう。p114
ラトゥールは客体としての客体というものを否定する。
例えばパストゥールは「しかるべき実験室を自分の手で注意深く設定したからこそ乳酸酵母は実在する」。パストゥールは超越性を作った、と言う。
考えてみれば、超越を製作することは、それほどめずらしいことではない。「自分の書いた文章を読むことで自分の考えていることが初めて分かる書き手」というものはよく居る。p115
人と物との注意深い共同作業によって構築された「物神事実」こそが実在である。
自由とは物神事実のかたわらで生きるということである。それは物神に支配されることではない。制御不可能な領域(撹乱的要素)を残すことである。〈 〉に注ぎ込まれるべき力の可能性を信じることである。
絶対王権を革命したとしても、「良い支配者」「固定された主体」による支配という構図が変わらないが、それでは意味がないのだ。p116
自由とは、他者の影響を遮断することではない。恐怖を騙して魅力に変え、風通しをよくしていく。諸々の繋がりを剥奪されないようにする。魅力によって人々を繋いでいけるのだ。p117
フェティッシュは排除されなければならないという思い込みは強い。真理や客観性や聖性に到達するには媒介物を完全に駆除するのが不可欠だと考えられているのだ。
しかし、我々が神自体に触ることができない以上、像的媒介物には超越へ達する手段を超えた聖性がすでにあると考えるべきではないか。
物神事実という認識から始める必要がある。「物神と事実、疎外と解放、非合理と合理などの階層的二元性に基づいて、双方の差異を絶対化するのではなく、モノもコトもヒトも諸々の結びつきによって相対的に異なるにすぎないのだとまずは認識すべきである。」とラトゥールは言う。(この文章は日本では危険である、と指摘しておいた方がよいだろう。日本では味噌もクソも一緒くたにして、結局権力側つまり日本的包括者が勝利するシステムが強く働くから)
「価値の階層化から注意深く距離を取りながら、価値の恣意性のなかから、いかにして新しい同一性をつくり直し、良い結びつきを通じて新たな社会関係を創造していくか」、「理論」をヒントにすることによってそれができるとラトゥールは言う。(マンガ、アニメなどで、女子どものたあいのない思いからかなり高度なドラマを作り続けてきた、日本人の膨大な諸作品は参考になるかもしれない。)
「いまここで新しい社会的現実を創造しようと思うのなら、そこには必ず「詐欺」の要素がなくてはならないということだ。」
「詐欺」というと誤解されるであろうが、なんらかのフェティッシュ「人知が及び難い領域があると思わせること」なしには、「一定の理念を巨大な現実に変えることができる集団的力を引き出すよすがにはなりえない」のだ。
未開社会の藁人形、アナキストの巨大人形、そしてホッブスのリバイアサンというのがその例だ。
「新しい社会形態や制度を創造するためには聖なるものが必要です。」「しかし、聖なるものの力と神秘は、同時に危険なものもあります」そして実践的にこの矛盾を解く方法はある、とグレーバーは言う。
わたしたちの社会で最も力をふるっているのは商品フェティシズムである。それは金融権力に識らず知らず服従するといったかたちでも、ひそかにどんどん進行している。
しかし、そのようなフェティシズムのなかで、それを拒否するのではなく、それを魅力ある結び目に変えていくということはできるのだ、と大黒氏は最後に言う。
近代の〈物神事実〉崇拝について ―ならびに「聖像衝突」 –2017
ブリュノ・ラトゥール (Bruno Latour 著), 荒金直人 (翻訳)
資本主義後の世界のために (新しいアナーキズムの視座) – 2009
デヴィッド グレーバー (著), 高祖 岩三郎 (翻訳)
(私はまだ読んでない)