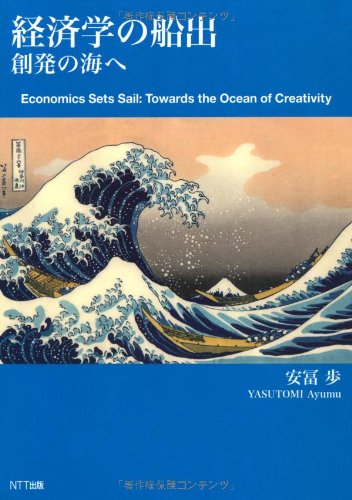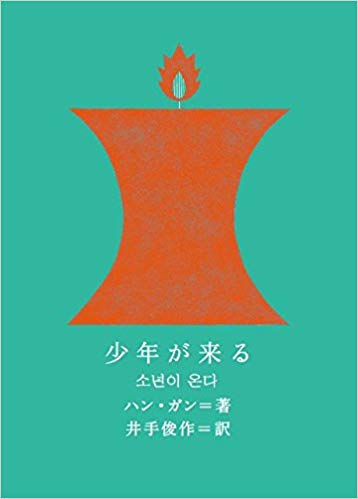(改稿中)
カテゴリー: book
黄晳暎『パリデギ』、火の海・血の海・砂の海を越えて
『パリデギ』は黄晳暎(ファン・ソギョン 1943-)という韓国の作家の書いた小説。
副題が「脱北少女の物語」という。2008年に刊行されたこの本は前に図書館で見たのだが、脱北女性の物語は『北朝鮮に嫁いで四十年 ある脱北日本人妻の手記』斉藤博子著
や映画マダムBなどいくつか知っているので、すぐに読まなくてもいいかと思ったのだ。
飢餓に至る困窮に対して、道端のクズを拾って売るなど血みどろの労苦の末に生き延びるリアリズムを、そうした本は表現している。それとそのような境遇を強いた国家(金一族)への呪詛と。
一方、この本はそうした本とはかなり違っている。
主人公は夢見る少女である。ただその夢は甘くふわふわしたものではない。困窮のうちに数千年生き延びてきたアジアの低層民が語り伝えてきた奇妙なおとぎ話。
ある春の日。門を開けると、私(5歳)より少し大きな女の子が立っていた。その子は白い木綿のつんつるてんのチマ・チョゴリを着ていた。主人公のパリは霊感の強い少女だった。それはおばあちゃんから受け継いだものだ。「あれはね、伝染病の鬼神なのさ」とおばあちゃんはいう。柳田國男的な話。
パリ一家は豆満江沿いの国境の町に引っ越す。
「前に美姉さんと豆満江に行った時、水に浮かんでゆっくり流れてくる人の姿が見えた。幼な児をおぶったままの母親の死体だった。きっと、母親と子どもが一緒に死んだのだ。美姉さんと私は、以前ならびっくりして悲鳴をあげ、誰かを呼びに走っただろうが、その時は息をこらして見つめていた。死体の後ろには、解けて長く伸びたねんねこの帯が揺らぎながら流れていた。」
数百万人が餓死したとも言われる90年代中期の北朝鮮。その悲劇を黄晳暎はこのように静かに描き出す。死体が流れてくる、それに対して悲鳴も上げずにじっとながめているまだ幼い少女たち。そこには、無残な死が幾分かは自分自身の未来にもあるかもしれないといった予感さえ孕まれていたかもしれない。
飢餓が激しくなるころ事件が起こり、一家は離散する。パリは賢(ヒョン)姉さんとおばあさんとともに川を越え、中国に入る。中国人の家に一時厄介になるが、そこも出なければならなくなり、裏山に穴を掘り住むことにする。
ここで、おばあさんがパリ王女のお話をしてくれる。その話はパリ王女が、両親とみんなを助けるために、生命水を取りに西天の果にまで行く話。ひとりの悲惨な脱北少女の悲惨な話に、このおとぎ話を二重に重ねていくといった構造をこの小説は取っている。死者や死者の世界との媒介をしてくれる愛犬と幻のなかで交流できるという神秘的能力をパリはもっていた。
物語は本の半ばで大きく回転する。パリは運命のいたずらにより、人身売買の犠牲になり、はるかロンドンに運ばれる。そこで彼女はまたゼロから難民としての生を生き直す。
私が冒頭で上げた2つの脱北女性、斉藤さんは日本へ、マダムBは韓国に帰る。詳しい話は省略するが話は東アジア3国で完結している。
しかしパリデギの場合は遠く、ロンドンに行きそこで終わっているのだ。パリはそこでパキスタン系の青年と出会い結婚する。しかしその相手はなんと911後のイスラム青年たちの熱狂に巻き込まれ行方不明になってしまう。
話が錯綜しすぎのような気がするが、そうではない。この小説はダンテの神曲のように、究極的な問いに答えようとしているのだ。問いとは、なぜ彼らは、300万人を越すとも言われる膨大な北朝鮮人は無残にも、死んでいかなければならなかったのか。その惨禍は数年続き、隣国であり繁栄を謳歌していた韓国と日本は、それを知ろうとすれば十分知り得たはずだ。しかし私たちのしたことは徹底的な無視だった。
飢えて死に、病気で死に、苦しんで死に、痛ましく死んだその膨大な人たちは、何も言えずに死んでいった。「すぐ答えておくれ。どんな理由で、わたしたちは苦痛を受けたのか?」
パリは問いを受け止め、試練の旅を続けざるをえない。パリは魔王と戦い、生命水を飲み帰ってくる。「わしらの死の意味を言ってみろ!」この問いに答えるために。
この問いには答えが与えられるが、その答えはあまり成功しているようには私には思えない。
ただ、「脱北」という巨大な悲惨を、どのような問いとして再構成したのか?
東アジアに閉ざされた国家内部の悲劇として描いてしまってはそれは違う、と彼は思った。
古くさいようなおとぎ話(火の海、血の海、砂の海を越えていく話)と二重重ねすることにより、かえって普遍的な膨大な悲惨の只中の生を浮かびあがらせることができると、黄晳暎は考えたのだろう。
1894年7月23日の朝鮮王宮占拠
7月ソウルへ、4日ほど行った。帰ってきて、徴用工問題からホワイト国除外問題、韓国側の反応や韓国からの旅行者が激減してしまったこと、あいちトリエンナーレでの「慰安婦像」に対する河村名古屋市長発言など、日本人の韓国認識の根幹に関わる問題が起こり、日韓関係は最悪となっています。この間わたしも少しだけ韓国について勉強しました。今まで不勉強だったことに今更ながら気づいた、わけですね。
1895年日清戦争において日本は短期間の戦いで、3億円以上の賠償金を獲得しました。これは、日本の大国化の途中の最も輝かしいできごとでした。主人公は外相陸奥宗光。「力ある者が何でもできるのは、帝国主義時代のならいである」、それを「冷静、現実的」にやりとげた「陸奥外交」こそ帝国主義の真髄である、と岡崎久彦は書いています。(1)
1894年東学の乱がおこると、「清国は朝鮮政府の要請を受けて出兵するとともに、天津条約に従ってこれを日本に通知し、日本もこれに対抗して出兵した。農民軍はこれをみて急ぎ朝鮮政府と和解したが、日清両国は朝鮮の内政改革をめぐって対立を深め、交戦状態に入った。」と山川出版社の『詳説日本史』には書いてあります。
戦争を始めるためには大義名分が要ります。「この上戦争の〈名〉はいかが相い成り候や、日本より無理に差し迫り、〈無名〉の戦争と相い成らざるよう祈る」と明治天皇側近も心配していました。(2)
「1876年江華条約一条に「朝鮮国は自主の邦にして」とある。現在朝鮮に清朝の軍隊が居るのは条約違反。撤兵要求しそれに応じないときは日本が代わって戦う。」というのが陸奥が考えた戦争の大義でした。
しかしその為には朝鮮政府から日本政府が「清軍駆逐」の依頼をもらう必要があります。しかし朝鮮王はださない。ではどうするか?
すでに1894.6.2日本軍は仁川に上陸していました。陸奥外相以下日本の総力をあげて、ソウルの朝鮮軍を一掃する計画が作られ、実行されました。
その核心部分は、王宮占拠、国王の捕獲、大院君を担ぎ出し日本の傀儡とすることです。
1894.7.23の王宮占拠の詳細を、金重明「物語朝鮮王朝の滅亡」という本から転記してみます。
漢城の日本軍は、周到な準備の末七月二十三日深夜、朝鮮の王宮、景福宮を取り囲み、一隊を王宮内に突入させた。
まず工兵隊が迎秋門の爆破を試みるが、爆薬が不足してうまくいかない。斧で打ち破ろうとするがこれも失敗する。最後は何人かの兵に塀を乗り越えさせ、内外よりのこぎりでかんぬきを裁断して、門を破った。この作業に手間取ったため、迎秋門突入は午前五時頃となってしまった。
王宮内に突入した日本軍は国王を擒(とりこ)とするため、ただちに捜索を開始する。
当時王宮侍衛隊は精兵といわれていた平壌の兵五百から編制されていた。王宮侍衛隊は四倍以上の日本軍に対し果敢に抵抗した。銃撃戦は数時間続き、双方に死傷者が出た。しかし衆寡敵せず、次第に侍衛隊は北方へ追い詰められていく。その間、日本軍の一隊が雍和門(ようわもん)内にいた国王を擒にしてしまう。
そしてついに、王から侍衛隊に、それ以上の抵抗はやめるようにとの命令が下るのである。王命に逆らうわけにはいかない。兵たちは悲憤律慨しながら、北方へ逃亡する。
日本軍はただちに、王宮と漢城内の朝鮮軍の武装解除にのりだす。分捕った武器は、大砲三十門、機関砲八門、小銃三千挺、雑武器無数であった。
さらに王宮に入った大鳥圭介は、兵を動員して王宮に所蔵されていた貴重な文化財をことごとく略奪し、仁川港から運び出してしまった。
国王を檎にした日本軍は、閔氏政権を打倒して、開化派を中心とした親日派政権を打ち立てるのである。(p149)
1894.8.20「日韓暫定合同条款」を日本は朝鮮に結ばせる。第4項が「本年7月23日王宮近傍において起こりたる両国兵員偶爾衝突事件は彼此共に之を追究せざるべし」です。真相を朝鮮側が口にしてはいけないと固く口止めしたのです。
日本政府は、事件当初からこの事件を、偶発的発砲が韓国側からあったので応戦した、という虚偽のストーリーにして、それだけを語り続けました。百年後の1994年に中塚が福島県立図書館で新資料を発掘するまでそのウソはくつがえされませんでした。普通の日本人は教えられていません。
しかし、日韓関係の原点とも言うべきこの暴虐な事件を知っておく必要はあるでしょう。日本国家の汚点であるからこそ。(2019.9.27)
(1)中塚明『現代日本の歴史認識』p215 から孫引。
(2)中塚明『現代日本の歴史認識』p199。
柴原浦子と近代日本
藤目ゆき氏の『性の歴史学』と題されてた本を読んだので、感想を書きたい。1997年出版。不二出版。
性愛、出産、家族といったものは、プライベートにして自然な領域とされ語られず思考の対象にならなかった。しかし実際はそれ自体が、近代によってあたらしく生み出されたといっていいほどの大きな変容を受けているものなのだ。
近代とは何か?近代というものが耐え難いほどの大きな痛み〜裂け目(slits)に向き合うことであるなら、それを端的に示すのは次のようなエピソードだろう。
「洋の東西を問わず、(性病)診断は、これを強制される女性にとって甚だしい恥辱だった。」
「英国植民地のインドでは、1880年代に性病検診の屈辱に耐えかねた女性たちが何千人も逃亡し、逃げ延びる先もなく餓死に瀕したといわれる。
しかし、性病検診の強制を性病予防という「文明」の顕現とみなす人々は、これを歓迎し日本に導入した。」
「「衆妓たとえ如何様ありても、この治療は受けがたしとて或いは声を揚げて泣き、あるいは遁れんとして狂走せしが、一室に鎖したれば、一人残らず改められ、大蛇の口を遁れたるものなかりしとぞ」という暴力的な実施が始まる。
官憲が立会い、衆人監視のもとで下半身をさらされ、またなれない医師が怪我をさせたり、実験材料にされたりすることもあった。逃亡する者、検査日だけ姿を隠す者、さらには自殺する女性もいた。」(p91)
わたしたちは約150年ほど前から近代化を受け入れた。幼い頃から小学校に通い、先生の言うことを聞き理解し覚えていくように自分の身体を変えていく。
公娼制度の導入においては、近代と身体はもっと劇的に出会う。女性のプライバシーの核心とされる性器に、近代の光をあて、注視する行為は、近代というものにはじめて出会う無学な女性たちにとって非常に暴力的なものであっただろう。
そういうふうに、近代公娼制度は日本に導入されていく。
公娼制度はナポレオン時代にパリで始まったもの、軍隊の慰安と性病の管理を基軸とする国家管理売春の体系である。(p409)
日本軍慰安婦制度との対比において、公娼制度は合法的な自然な市民に開かれた制度であるかにイメージされることが多い。しかしそれはまったく違っており、公娼制度もまた基本的に国軍のための制度である。
「日本の公娼制度は明治新政権の下で近代的に再編され、人民収奪体系として機能し、日本の下層階級の女性と植民地の女性たちを組み入れて発展していく。遊郭は地域に巨額な金をおとし商業者を潤し、国家とその地方庁は娼婦からの直接的間接的徴税で莫大な財政収入を獲得でき、軍隊は買春によって性病にかかる心配なく「慰安」される。」(p410)これが近代国家における公娼制の重要性である。
1880年群馬県のクリスチャン民権家によって始まった廃娼運動は91年「廃娼令」を勝ち取る。全国には波及しなかったものの日本キリスト教婦人矯風会などを中心とする廃娼運動は粘り強く続いていく。
しかし、藤目は村上信彦らの先行者と異なりこうした運動への評価は低い。
一つは、「群馬廃娼後の娼妓たちの多くは、他府県で娼妓を続けるか、県内で類似の接客業に転業している」(p101)
もう一つ藤目の強調するのは矯風会婦人活動家たちが持っていた「醜業婦」観である。日本では本来、「売春に従事した女性が「消すことのできぬ烙印をおされるようなこともなく、したがって結婚もできるし、そしてまた実際に婚姻」した。婚姻外の性関係を罪悪視し、「純潔」でない女性に汚名をきせ排除するというのは西欧的価値観」である。しかるに日本の廃娼運動家はこの価値観をしっかり受容した。娼婦はその存在自体が悪であるという窮極の差別に繋がりうるものであり、娼婦たちの救済には役立たない。
このような状況のなかで、柴原浦子というひとりの女性を、藤目は肯定的に大きく取り上げている。
柴原浦子 1887年生 広島県の田舎で生まれ、看護婦の資格を取る。医師と結婚するが間もなく離婚。看護婦に比べ生活の安定を得られる職業である産婆の資格を取る。1910年頃から、出産時の死亡率の改善のため「新産婆」の普及が国策となっていた。
広島県の産婆なき村で開業し、極貧の家庭のためにも献身的に仕事をした。また衛生思想の普及にも努めた。
1920年頃から、「婦人の徳の涵養」、婦人選挙権、産児制限運動などにとりくむ各種婦人運動が盛んになった。
当時の貧しい母親の多くは子沢山に悩んでいた。彼女たちに寄り添おうとして柴原は産児制限運動に邁進する。
1930年、そうした運動の中心地の一つ大阪(天王寺の南方、釜ヶ崎、飛田の近く)に、産児制限の相談所を彼女は開設、相談者が殺到する。貧困による産児調節を求めて為政者とも対立する。
1931年満州事変勃発以降、「産めよ殖やせよ」がスローガンになり、産児制限運動への弾圧も厳しくなる。困難に陥った女性を助けようとする柴原は、非公然の中絶を助けることもあった。お上品な正義感や時代の流れなど気にせず自分が取り組むべき事象にたちむかった柴原は、1933年堕胎罪で起訴され有罪となる。執行猶予中もなお彼女は行為を改めず、1935年再び検挙、1年5ヶ月の実刑判決を受ける。
戦時期は奈良県大和小泉の被差別部落に入り、助産、避妊指導、妊娠中絶を引き受けた。
しかし彼女は「天皇様のためにやっている」と語っていた。どんなに貧しくてもみな「天皇様の赤子」であり平等なのだ、という信念である。
私は彼女の生き方を知って感心した。一方で産児制限や階級闘争についての数限りない難しい論争がある。そのような理論や論争に生涯を傾ける値打ちがあるのか。正しい理論は正しい生き方を保証しない。権力の弾圧に負け何らかの転向を余儀なくされるだけだろう。一方で左翼でなかった柴原は、敗戦までの時期、貧者の生殖の困難という問題を救うという目的を弾圧にもめげず貫いた。
正しい生き方をしたいとは私は実はあまり思っていない。しかし何が正しいのか。正しい思想を獲得することより大事なことがある、という結論にもなる。柴原の生き方を素直に考えると。
柴原浦子は藤目氏以外に取り上げる人もおらずほぼ忘れられているようだが、偉大な人物としてもっと知られるべきではないかと思う。
さてもうひとつ、藤目が肯定的にとりあげているのは、次の運動だ。
戦後1956年、売春防止法が成立の直前、赤線で働く女性たちは法案が通ると、今よりひどい違法なヤクザなどに支配される(青線、白線)に移行せざるを得ないことをおそれ、法案に反対していた。東京都女子従業員連合会を作り4500人が加入した。生業を一挙に違法化し奪う以上、更生資金を要求しようとしたのだ。しかしその要求は相手にされなかった。その国家の態度の背後には、売春婦は醜業婦であるとする廃娼運動女性たち自身の偏見もあったと藤目は指摘する。
1991年金学順のカムアウトからいわゆる慰安婦問題は始まった。日本のフェミニストたちが慰安婦問題を知らなかったはずはない。(同じような名前である従軍看護婦体験者たちが一番良く知っていたはずだ。でも語っているのは見たことがない。)
かって廃娼運動家たちは「大日本帝国の海外膨張を疑わず「醜業婦」を取り締り軍隊を保護せんとする志向と娼婦に心を寄せるよりも妻・母として夫・息子を「誘惑する」娼婦に反感をいだく心性」をもっていた(p323)。戦後国会議員などになっていった彼女たちの後輩たちの心根もそれほどは、変化していなかったのではないか。それが「慰安婦」に対する46年間の沈黙につながったのではないか。まあそのような推測も少しはあたっているであろう。
『性の歴史学』分厚く地味な本だが、いまだ「慰安婦問題」から抜け出せない日本を根底から考える上でも読んでおきたい本である。
自分自身のあり方を見つめ直すことで、新たな創発を起こす
安冨歩『経済学の船出』NTT出版に興味を持っている人が多いようだ。品切れで高価になっているので余計に。
「普通の人の普通の感覚というものは、意外に鋭いものであり、「なんだか変だな」と感じることには、それなりの理由が潜んでいる。」
というのが「はじめに」の最初の文章。
「読者がその感覚を把持し、奇妙なものごとに出会ったときに、「まあいいか」とやり過ごさず、自分自身の内的ダイナミズムに基づいて、独自の思考を展開するための手がかりを提供すること、これが本書の目指すところである」と書いている。
我々にできることは温故知新(論語)だけだ。つまり「すでにあるものについてよく考え、自分自身のあり方を見つめ直すことで、新たな創発を起こすこと」であると。
しかしわれわれはしばしば良識の作動を失う。付和雷同する自動人形になる。
バブル経済やアジア太平洋戦争になだれこんだこと、はては産業革命以来の驚くべき経済発展を続ける人類全体も、付和雷同のうねりだ(と見ることもできよう)とされる。ii
「良識の作動を押し殺す正当化の屁理屈を振り回すことは、まぎれもない暴力である。」本来の常識に敵対するものが、「正当化の屁理屈」である。実は屁理屈にすぎないものが、「社会常識」として大きな顔をして世の中を支配して居たりする。「各人が自分自身の感覚に立ち戻り」さらに「各人の良識の作動を促すマネジメント」をすることができれば、どちらが屁理屈かは分かる。
以上が「はじめに」の最初の部分である。
「自分自身のあり方を見つめ直すことで、新たな創発を起こす」は、彼自身言うように古臭い徳目とも見える。しかし、効率や利潤というものを目指して、わたしたちの社会はむちゃくちゃになりつつあるのに、それに変わるべき価値を提示できていない。そうである以上「創発」という言葉が耳慣れないとか言っている場合ではないだろう。
第2章は、網野善彦の無縁論を扱う。
共同体=有縁/市場=無縁 といったふうに理解されがちであるが、それは(厳密には)違う。
「縁結び→←縁切り」というダイナミックな二つの行為を原理として取り出すことが大事なのだ。p51
アメリカの哲学者フィンガレットは「人間は魔法を使える」と言う。
「我々は日常生活のなかで魔法を頻繁に使っている。たとえば私が大学で歩いていると、向こうから学生がやってくる。向こうも私に気づく。私が笑顔で頭を下げると、学生も一緒に頭を下げて、そのまま無言で通り過ぎる。このとき私は、適切なタイミングで適切な頭を下げるしぐさをすることで、何らの強制力も使うことなく、学生の頭を下げさせることに成功している。」p56
複雑で微妙な操作をうまく組み合わせること、それはあえていえばそこに神秘性を込めることに成功することである。
この魔法は、儒教の「礼」を言い換えたものである。
このような魔法により、人は他人に依存して生きていくことができる。p58
こうした神秘的相互了解なしに、むりやり他人を動かそうとするのがハラスメントである。無縁の原理は、「魔法」がハラスメントに堕落するのを防止する機能を持っているということができる。
わたしたちの社会は、経済学をはじめとする「屁理屈」に厚く覆われている。だからそのことに気づくだけでも容易ではない。しかしこの本を読んで、再出発(船出)していくことはできるだろう。
経済学の船出(アマゾン) 中身検索あり
ハン・ガン『ギリシア語の時間』について
わたしたちの生が、不可思議な条件によって組み合わされた不細工な人形のごときものであること。
だから、それはふとしたきっかけで崩れてしまい、むねに大きな空洞が空いたままいきていく、そうしたものであること。ハン・ガンの人間観はそうしたものだ。
自分を主体であると、錯覚してはいけない。そうではなく、インターフェイスとしての自己、という発想がむしろ必要なのだ。
言葉によって世界が成立している以上、言葉は意識されない透明なものでなければならない。
言葉が存在を主張し始めると、存在者からなる世界は
どうしていいか、分からなくなる。
いちばん辛いのは、自分の口から出た言葉の一つひとつが
鳥肌がたつほどはっきり聞こえることだった。どんな
ありきたりの文章も、その完全さと不完全さ、真実と嘘、美しさと醜さを
氷のように冷ややかにくっきりあばきたてる。彼女は自分の
舌と手から吐き出される、白い蜘蛛の糸のような文章を恥じた。
嘔吐したかった。悲鳴を上げたかった。(p16)
言葉を当たり前のように自由に使いこなし、つまり言葉を見ることも感じることもない、幸せな人たちと、ひとつひとつの言葉を直接感受し、痛みすら感じてしまう主人公。
言葉。「一つの文章を書き始めようとするたびに、古い心臓を彼女は感じる。ぼろぼろの、つぎをあてられ、繕われ、干からびた、無表情な心臓。(p197)」
自分のものではないのに自分のものであるかのような言葉。
その喪失と回復(の予感)についてのこの物語は、特殊でありながら、わたしたちの体験の奥にも通じているようだ。
三浦しおん『仏果を得ず』
三浦しおん『仏果を得ず』を読んだ。
文楽の義太夫語りの若者を描いた小説で面白かった。
女殺油地獄、日高川入相花王、ひらかな盛衰記、本朝二十四孝、妹背山婦女庭訓、仮名手本忠臣蔵 など、の演目を各章の題にしている。
これらの演目は、歌舞伎と共通しているものも多いから、名前くらいは知っている人は多い。しかし、中身にまで入っていこうとしてもけっこう難しい。
というのは、あらすじを聞いても、ピンとこないというか、違和感ばかりでそれ以上共感できないといった話も多いのだ。三浦は熱心な文楽ファンになったのだが、そうなるためには、自分なかで多くのそうした難問を解かなければならなかった。これはそのプロセスを小説という形に展開したものでもある。
「世話物の男は優柔不断で、見ていて腹のたつようなやつばかりだ。登場する女たちが、それでも主人公の男に惚れている理由は?」
三浦はずばりと問題点を指摘する。
人間はおろかなものだ。それは私にも分かる。しかし、わざわざそんなことを芝居にまでして何が面白いのだろうか。それを現在によみがえらせるために必死で芸を磨く。
おろかさにそれだけの値打ちがあるのだろうか?
主人公健太夫は、小説の前半、芸にだけ打ち込むストイックな生活をしている。しかし後半、不思議にも、二人の女性から愛され、愛し、自らおろかさをとことんさらさざるをえなくなるのだ。そしてそのおろかさは感動的でもある。
この小説は、文楽案内を小説の体裁にしてみたものというより、文楽の力を借りてそれを分かりやすく展開してみた、優れた小説だ。
ハン・ガンの『少年が来る』について
『少年が来る』という小説は傑作だと思う。光州事件を題材にしている。
書いたのは、ハン・ガンという1970年光州生まれの女性作家だ。彼女は10歳の時に光州事件に遭遇した勘定になるが、彼女の一家はその直前にソウルに引っ越している。
光州事件のことをよく知らないので復習する。
1979.10.26 朴大統領暗殺、キム・ジェギュ(金載圭)による。(『KCIA 南山の部長たち』に描かれている。)
79.12.12 全斗煥が軍の実権を握る。
80年春、ソウルの春 三金が政治の主役に。(光州は金大中氏の根拠地)
80.5.17 非常戒厳令全国に。
80.5.18 光州で無差別発砲事件が起こる
80.5.27 戒厳軍は武力鎮圧を強行。道庁内に留まっていた多数の市民の決死隊員を殺害した。
この市民決死隊のなかには、多くの若者、大学生、高校生、あるいは中学生までいた。この小説は少年、一人の中学生を中心に語られる。トンホ。
死体置き場になった尚武館。混乱のなかでここに迷い混んだ少年は、病院からどんどん運びこまれる棺を整理する係りになってしまう。死者の名前と棺の番号をノートに記入する係りだ。
チンス兄さんが50本入りのろうそく五箱とマッチ箱を置いていった朝、君は道庁の本館と別館を隅から隅まで回りながら、ろうそく台にする飲料の瓶を集めてきた。入り口の机の前に立って、一本ずつろうそくに火をつけてガラス瓶に挿しておくと、それを遺族が持っていって柩の前に置いた。
ろうそくの数にはゆとりがあり、遺族が寄り添っていない柩と身元が未確認の遺体の枕元にも漏れなくともすことができた。P25静かで美しい文章だ。実際には惨たらしく悪臭のする死体の山を、なんとかそれを並べてあげて、「悼む」形を整えた主人公の少年と二人の「姉さん」。かれらが並べたろうそくについて、それが悪臭を消すかのように美しく描写している。
彼がひとつ、不思議に思ったのは、短い追悼式で、遺族が愛国歌を歌うことだった。軍人が殺した人々にどうして愛国歌を歌ってあげるのだろうか?
君がそう訊くと、姉さんはかえって驚く。軍人が反乱を起こしたのだ、と。「君も見たじゃないの。真っ昼間に人々を殴って、突き刺して、それでも足りないみたいに銃で撃ったじゃないの。そうしろって彼らが命令したのよ。そんな彼らを私たちの祖国の人たちだと、どうして呼べるのよ。」(P22)
少年はいままで教えられていたとおり、愛国歌は国家とその軍を褒めたたえるものだと思っていた。軍人の独裁が終わり民主主義の時代がやってきたのに、それを逆転し、銃口で人をどんどん殺して権力を奪おうとしているのは、軍だ、彼らは何の誇りも持てない反乱者にすぎない。本来の国、ネーションは私たちの側にある、と姉さんは説明する。しかし、少年は容易にはその説明が理解できない。
これはこの小説にとってはトリビアルな部分に過ぎないかもしれない。しかし一方で、日本人はまだこの国歌=国家の問題を解決できていないという気が強くする。
(天皇の歌である君が代を戦後日本の国歌にしたのは少しまずかった。
でもそれ以上にまずかったのは、解決したはずの「慰安婦問題」をいつまでも問題にし続け、「徴用工」にまで問題を広げ、自由貿易の原則まで破って見せて、まだ落とし所を見出し得ない安倍政権のやりくちだろう。)
「恐怖のために集会の規模が急速に小さくなっていると彼は真剣な顔で言った。」
「あまりにも多くの血が流れたではないですか。その血を見なかったふりなどできるはずがありません。先に逝った方たちの魂が、目を見開いて私たちを見守っています。」
「魂には体がないのに、どうやって目を開けて僕たちを見守るんだろう。」(P28)少年はまだ幼いので、ぼんやりと考える。しかし少年は間違ってはいない。死者は死んでしまっており、彼らはどのようなベクトルも指示しはしない。すべては生きているこの私が決めることしかできない。
「軍人が圧倒的に強いということを知らないわけではありませんでした。ただ妙なことには、彼らの力と同じくらいに強烈な何かが私を圧倒していたということなのです。
良心。
そうです、良心。
この世で最も恐るべきものがそれです。
軍人が撃ち殺した人たちの遺体をリヤカーに載せ、先頭に押し立てて数十万の人々とともに銃口の前に立った日、不意に発見した自分の内にある清らかな何かに私は驚きました。もう何も怖くないという感じ、今死んでも構わないという感じ、数十万の人々の血が集まって巨大な血管をつくったようだった新鮮な感じを覚えています。その血管に流れ込んでドクドクと脈打つこの世で最も巨大で崇高な心臓の脈拍を私は感じました。大胆にも私がその一部になったのだと感じました。(p140-142)」
このような〈良心〉は最も大事なものであるのに、めったに語られることはない。言うまでもなく、代わりに語られるのは〈愛国〉であり、ある場合には〈革命〉だ。愛国は現在の体制・秩序・軍事組織への愛情・従順と区別するのが難しい。革命は運動の指導部あるいは前衛党への忠誠と区別するのが難しい。
「しかし今では何も確信することができません。(p142)」
といっても、この発言者四章「鉄と血」の主人公の「確信」が崩壊した原因は、明確に存在する。「モナミの黒のボールペン。それで指の間を縫うように挟み込みました。(p129)」以後10ページくらい詳細に語られる拷問の連続がそれだ。
敗北に続く拷問。
それが終わっても、日常生活がふつうに返ってくることはないのだ。生きることは存在の根っことともにしか営めないが、幸存者たちはみなそこに大きな欠損をうけてしまった。
271頁の小さな本だが、一つの軍事的弾圧の一面をクリアーに描いている。
(2023.8.11 ver.2)
梅原猛についての走り書き
『ユリイカ 梅原猛』というのを買った。最近日本古代を(簡単に)理解したいと思っているので。
梅原猛(うめはらたけし、1925年-2019年1月12日))(吉本の1年下)
出雲について
出雲は戦後長い間、古代の実在的勢力としては重視されていなかった。
「大和と出雲を結ぶものは実は宇宙軸であり、つまり大和から見て出雲が西の果にあって日の没する方位を代表していたことが出雲をして神話的に重からしめるゆえんであった。p99」と西郷信綱も書いていた。
「1984年に荒神谷遺跡から358本の銅剣が見つかり、翌年には6個の銅鐸と16本の銅矛が出土した。1996年には加茂岩倉遺跡から銅鐸39個が掘り出された。そして2000年、出雲大社の地下から巨大な柱が出土して」
「20年足らずの間に、直線で20キロも離れていない狭い地域で相次いだ3つの大発見によって、古代日本列島における出雲に対する認識はすっかり変わる」p103(べきであった)
梅原は「出雲を舞台にした「天の下造らしし大神」の話は、全くの虚構ではないかのか」と書いていた。p98
上記の発見から10年以上遅れて、2010年『葬られた王朝 古代出雲の謎を解く』で梅原は旧説を撤回した。p102
(研究者でも、出雲の実態的勢力はなかった説を墨守する人もまだいるらしい。)
鎌倉新仏教中心主義
戦後日本思想史では親鸞が重視される。「自己の罪悪を反省し、阿弥陀如来の絶対他力を確信し、その信仰のもと安心を享受するという内面のドラマ」p224(参照:子安)に注目する。要はプロテスタント的宗教に近づけた理解ということのようだ。
(鎌倉新仏教だけを強調する理解:「鎌倉時代以降を「封建制」と理解し、日本は東アジア諸国と違って「封建制」に到達したから近代化の道に進むことができたという「脱亜論」の変形である。p56)
それに対して、「自然は人間のように、生き、物言う世界」と信じる日本の神道と最も密接に結びつき定着した真言密教(p222)、そして天台(本覚論)を強調したのが初期梅原。
「密教が生み出した信仰である観音崇拝や不動崇拝は広く民衆の間に広がった。」p56
日本文化論
鈴木大拙や和辻哲郎、彼らの作り上げた日本文化論を 戦後継承することはできない。p55 として激しく批判するところから梅原の評論活動は始まった。
「現在では、鈴木も和辻もなかば忘れられているが」と保立はあっさり書く。
しかし、アカデミズムの側のそのむとんちゃくな忘却が、大衆に対して何重にも劣化した「日本主義」、日本会議系の、蔓延を許ししてしまったのではないのか?
和辻:国民精神文化研究所 戦後はそれについて口をぬぐった
和辻『尊王思想とその伝統』
1,祀る神としての天皇
2,その背後にいる 祀って祀られる皇祖神
3,風雨の神のような 祀られるだけの神
4,祀られるだけの 祟り神 p58
世界全部につながっちゃう
これまでの日本人が国粋的な意味で日本のオリジナルだと思っていたものが、実はもっと広い「古代世界」とつながっていて、聖徳太子をズルズルたどっていくとキリスト教につながり、世界全部につながっちゃうというように、日本というものが大きく底のほうで「世界」に開かれている p251
という普遍性を語るのが、梅原の仕事だった。
梅原は〈辺境〉に共感を持った。
〈辺境〉を糾合して普遍化し、人類思想のメインラインに位置づけようとした。p254
そして、それを大衆にわかり易い物語として語りきった。
歴史に血と肉が与えられて
山岸:ああ、すごいですねえ。本当に先生のお話を伺っていると、歴史に血と肉が与えられて生命が吹きこまれるという感じですね。(略)歴史の先生はというと、どうしても年号を並べて二言目には「かもしれません」ばかりおっしゃるでしょう。私、これが残念でしかたないんです。梅原先生のように、とても明快で歴史が生身で立ち上がってくるようにお話してくださると…。
梅原:それを言いすぎるから、ぼくは嫌われるんだ(笑)。
山岸:いえいえ。でも、それだけに影響力がすごくて、私は本当に怖くて(笑)。
『日出処の天子 3』白泉社文庫 解説・対談より
異なり記念日 感想
『異なり記念日』齋藤陽道 医学書院 という奇妙な題の本を読んだ。
ろう者である写真家が自分と家族のことを語ったエッセイ、といったもの。わたしたちは書記言語より先に音声言語(聞く・話す)に出会うわけだが、聞くことが困難である人たちがろう者だ。作者齋藤陽道は、自分たちのことをこう書く。「男の写真家は聴者の家庭で育ち、日本語に近づく教育を受けました(本格的に日本手話を使い始めたのは16歳のときです)。
女の写真家はろう者の家庭で育ち、生まれたときから日本手話で語り、聞きました。」
日本語(音声語)。
電話:「もしもし」「はるみちだよ」「どうしたの?」「これから帰るよ」「気をつけて帰ってきてね」・・・
あまりにも当たり前の日常会話だから特に活字にしたりすることもないやりとりだ。しかしろう者の陽道にとっては、電話でこうしたさりげないやり取りをすることは、大きな困難を乗り越えないとできないことであり、大変な憧れだった。
そして、彼は実際にそうした会話をしたわけではないのだという。「ガラス越しに見ている同級生たちに対する見栄としての、電話ができるフリだった。p125」
日本語は分かっている、しかし聴く・話す機能の一部にかなりの困難があるがために、この程度のことでもわざわざ「フィクション」としてしか実現できない。いや「この程度のこと」ではないのだ。
「ごくふつうに「聞こえる人」のように伝わり和えたというやりとりのなめらかさ」「そんななめらかな会話ができたときには(略)内心では痺れるくらいの喜びに満ちていた。p126」
これは、音声の感度も高度化した灰色のデジタル公衆電話がでてきた頃の話。その後、FAXができ、高校1年のころには、携帯電話でショートメールができるようになる。
高校三年のときには8〜10円で千文字ほどのメールを送れるサービス、その長文メールを一日に何通も書いていた。彼の喜びは想像することができる。彼の日本語に対する特殊な障害を乗り越え、友達と同じようにコミュニケーションできる喜び。
特異なこともない日常に向き合い一冊の本になるほど文字を紡ぎ出すこと、いままでの文学青年とまったく違った回路をたどり、彼は日本語と表現活動にたどりついているのだ。
言葉を身につけてしまった我々はどうしても言葉で考え言葉で伝えようとする。
ただ、コミュニケーションのためにはそれとは少し違ったやり方もあるのだ。
ろう者と自閉症者のコミュニケーション。
「まなみ(ろう者)が一言も音声を発さずに、身振り(でもおそらくそれはただの身振りではない。表情やちょっとした空間の揺らぎにも意味を含める手話言語のニュアンスを織り交ぜた身振りであって、メッセージがより明快に読み取れるものであることが予想できる)で語りかけた」
「その子の(想像だけど)「せっかちで落ち着きがない」動作から、目線やしぐさ、指先の震え、一瞬の表情といったものすべてを無意識に「ことば」として受け止めていたからこそ」
ろう者と自閉症者。辞書的言語以外の領域で語らざるをえない人同士といえるのかどうか、かれらの間ではコミュニケーションが成立した。
日本語(書記言語と音声言語)によって世界は、どんなわずかな隙間さえ無いほど、語りつけされ埋め尽くされているかのように感じられる。しかしほんとうはまったくそのようなことはないのだ。
この本は若い夫婦が子供という他者とどう出会うかという話でもある。子供はいつも言葉なしに生まれてくる。そして親たちとの圧倒的な接触のなかで言葉も身につけていく。この夫婦の場合は、両親は聞こえないというハンディを持ち、子供は(たぶん)持たない。それでも子供は親から言葉を学んでいく。その体験を作者は〈異なり〉の体験として書き留める。子供がはじめて音楽というものを知り嬉しそうに報告してくれる。作者は思わず「おとーさん、音楽、わからない。わからないんだよね。」と返してしまう。
〈異なり〉の体験は、辛いものではある。しかし、生きることの豊かさと繋がってもいるのだ。
わたしたちは〈ろう者〉と無縁に、これからも生きていくかもしれない。しかし、この本を読むことで、言葉の、生きることの豊かさに触れるきっかけに出会うことができるかもしれない。