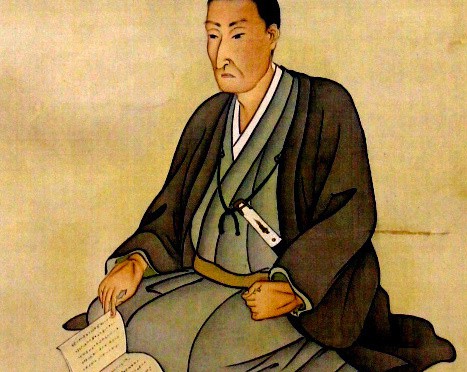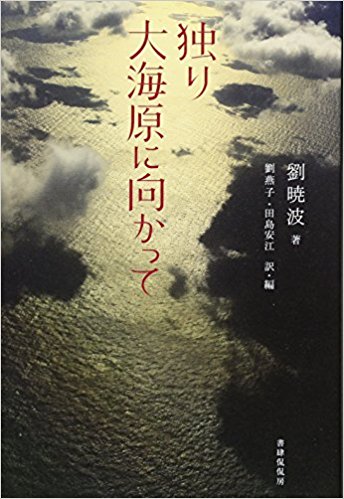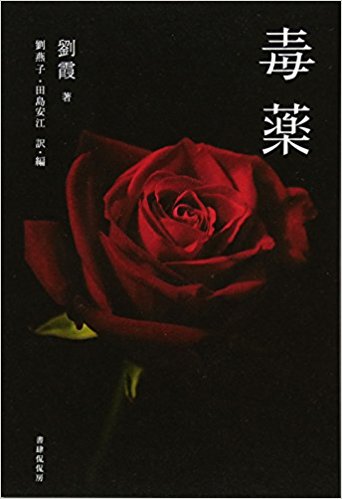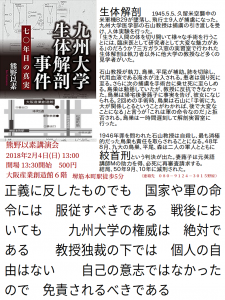『ジュディス・バトラー』藤高和輝・以文社という本を読んだ。借り出し期間超過しているので、今日図書館に返す。バトラー論としては読みやすいし良い本だと思う。
さて、バトラー思想を「生と哲学を賭けた闘い」として理解するのだとして、藤高(敬称略)は、この本を書いた。
社会という制度のなかで他者化され押し殺されてきた彼女自身の生、と哲学という制度のなかで他者化され押し殺されてきたわたしたちの生、その両方を生き延びさせるために虚数方向から他者の声を呼び込むこと、それが彼女の闘いであっただろう。
バトラーは何よりもトラブルの哲学者として記憶されている。幼少期、自身のジェンダーやセクシュアリティをめぐる葛藤から、地下室に逃亡し、スピノザのエチカを手に取った。「人間存在におけるコナトゥスの根源的な固執から生じる感情の状態に関する推論は、人間の感情に関するもっとも深く、純粋で優れた説明のように思えた。事物がその存在で在り続けようとする。私に送られたこの思想は、絶望のなかでさえ固執する一種の生気論であるように思われた。」p19 とバトラーは語っている。
エチカ2部定理九:現実に存在する個物の観念は、神が無限である限りにおいてではなく神が現実に存在する他の個物の観念に変状(アフェクトゥス)した〔発現した〕と見られる限りにおいて神を原因とする。バトラーが周囲とうまくいかない「醜いこ」であったとすれば、自己がどのような変状であろうと神との関係においては、他の子とまったき対等性を持つ、と教えられることは根源的慰めを与えてくれるものであっただろう。
(エチカの引用は、http://666999.info/liu/ethica.php の目次を利用した。)
エチカ3部定理七:おのおのの物が自己の有に固執しようと努める努力(要請・コナトゥス)は、その物の現実的本質にほかならない。とある。
「物はその定まった本性から必然的に生ずること以外のいかなることをもなしえない」というスピノザの説明から私は決定論的印象しかうけなかった。しかし、「要請」は事実的現実に尽きるものではなく事実的現実の彼方へ向かおうとする要請を内に含んでいることを意味している、とアガンベンは言っているらしい。p290
同一性に固執しようとすることが、かえって差異の立体性を開いてしまうといった逆説が展開されていく。
コナトゥス、事物が生来持っている、存在し、自らを高めつづけようとする傾向を言う。(ウィキペディア)自己保存。とても個人主義的な概念だと思われていたが、バトラーはそのベクトルの向きを変えようとした。ドゥルーズは、コナトゥスはそれが存在する状況に即して自らを表現するとした。
バトラーはレズビアンのアイデンティティ政治とかの中から出てきた学者でもある。「ひとが自分自身の存在に固執することが可能になるのは、他性への固執によってのみである」p254 ヘテロなマジョリティとちがって、容易に自己同一性を獲得できないのがレズビアン(など)であって、トラブルや過剰の考察が常に必要になる。
社会はまず承認の規範的構造として、傷つきやすい「わたし」の前に現れる。でわたしはまず、規範に服従しなければならない。
子供の場合、まず「自分自身として存続するためには、誰かに愛着しなければならない」p260 そしてもし養育者に認めてもらえないならば、社会的な死を経験しなければならない。その為子供は「従属化」を選ぶ。自分自身の従属化の諸条件を欲望することになる。服従化への欲望、つまり死の欲動。主体として認められるためには、ひとは自己を断念し解体せねばならない。p260
他者の世界に服従すること、それが自分自身の存在への固執になる。なんだか非常に暗い話だ。ただまあ、現在の日本社会は学校教育、就活、過剰なサービス、死に至る残業と、「服従」ばかりであることは確かな気もする。
ひとは承認を求める、つまり規範への服従を全力で行なう。しかし、そうではない可能性もある。承認の規範的構造に対して批判的な開かれを迫っていくこと、自分自身の存在を賭け、「生成変化」の実践になっていくことができる。p264
バトラーはコナトゥス(自己保存)から出発する。しかし自分自身の存在への固執が規範的構造とトラブってしまう時、規範の方が変化していく可能性がある。
コナトゥスというベクトルが存在の自らを高めつづけようとする傾向に従いつつも、社会から見た見た時、ベクトルの方向を変える。このような変容を研究していきたいと私は考えている。
批判は常に社会的歴史的地平の内部でしか行われ得ない。が、どのように知と権力が世界を体系化し秩序化しているかを明らかにする。それと、そこからの脱出を示すブレイキング・ポイントを示すことができると、フーコーは、言う。主体は脱服従化できるのだ。
〈開かれ〉をフーコーは示す。真理の体制の限界を疑問に付し、同時に自己をある意味で危険に曝す。それは、ある者を承認したい、あるいは別の者によって承認されたいという欲望によって動機づけられている、とバトラーは付け加える。
私は、社会ー歴史的地平のなかで行為しながら、それを破綻、あるいは変容させようとしている。私を私自身の外の、私自身から剥奪され、同時に私が主体として構成されるような場へと移動させる動き、脱自的運動を通して。p280 それは他者とともに生きる共通の生を開く徳の実践でもある。
マイノリティは暴力的抑圧によって形成される。それは、暴力的な報復に向かいやすいものでもある。私たちという存在は、共有された危うさである。しかしそうした怒りは、私たちが強い情動でもって互いに結び付けられるための条件でもあるのだ。
承認可能性の規範から排除された「怒り」を自己や他者に向けるのではなく、社会へ向けなおすことで「共通の生」を開こうとする、そうした可能性がある。
「抵抗の行為はある生の様式にノーと言うものであるとともに、もう一つの生の様式にイエスと言うものであろう」p285
「怒り」を、あなたとの新たな関係への、新たな共同性へのベクトルに変容させること。私たちという同一性を確立し、他者を排除するのがアインデンティティ・ポリティクスの経験だったが、バトラーはそれをきちんと辿ろうとすることで、かえって「共通の生」を志向することになった。
「もし主体の系譜学的批判が現在の言説上の手段によって形成される構成的、排他的な権力関係に対する問いかけであるならば、それに従って、クィア主体についての批判はクィア・ポリティックスの民主化の継続に欠かせないものであるだろう。アイデンティティ用語が使われるべきであり、「アウトであること」が肯定されるべきであるのと同様に、これらの概念自体が生産する排他的作用は批判されなければならない。」
アイデンティティ・ポリティクスとは領域確定であり、定義の厳密化であり、自己権力の確立であるだろう。しかし、バトラーはそこに留まらない。「批判的にクィアする」ことが継続されなければならない。批判的に「自己の外へ」と開こうとする運動、〈取り乱し・トラブル〉は幸か不幸か、継続される。
「すなわち、潜往的に運動しているものとして、時間的なものとして、私ではないもの(not I)として、固定した利害あるいは経験よりもむしろ求め(want)の系譜学に従って脱構築しうるものとして、である。このように、(現有進行中の)欲望の系譜学の効果として理解された主体は[…]主権的なものとしても、決定的なものとしても現れない。たとえ、それが「私」として肯定されているときでさえ(Brown 1995: 75)。」
と、ウェンディ・ブラウンが引用される。p302
つまり運動は、断固としたわたし(あるいは私たち)の肯定として始まるが、求めるという動詞に導かれるそれは、同一化、権力集中の力学から常に逸脱することを孕んでいる。
バトラーは〈複数形の私たち〉に訴えるのだ。
以上、この本の9章、10章、結論部を、自由かつきままに要約してみた。怒られるかもしれない。
ご批判などよろしくおねがいします。