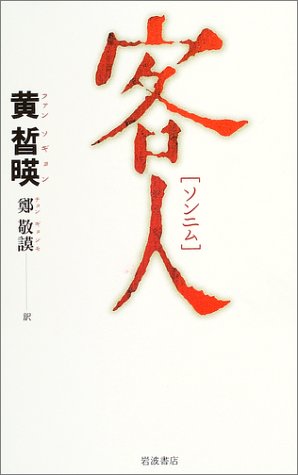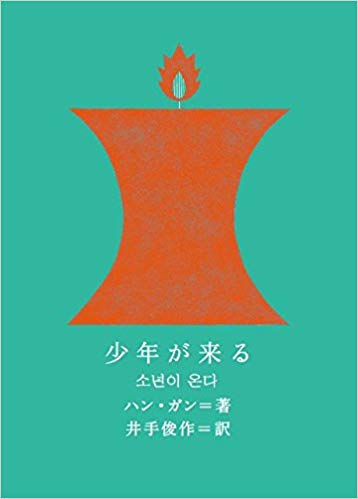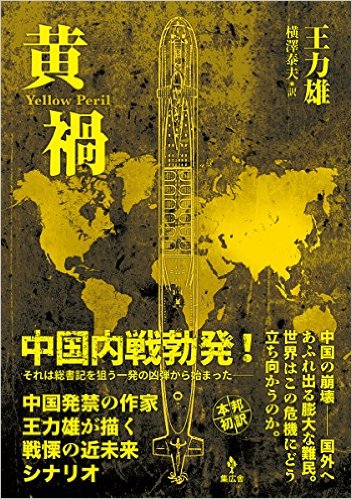1, キリスト教徒青年たちによる殺戮
黄晳暎(ファンソギョン)の『客人』という小説、2003年に出版され翌年すぐ翻訳された本(岩波書店)、すこし古びた本を図書館でなんとなく手に取った。(訳者鄭敬謨、チョンギョンモ)
この小説はすごい。非常に残虐な出来事を直視し、書いているがエグくならず押し付けがましくもなく読むことができる。非常に大きなテーマを見事に描ききった傑作だと思う。
柳ヨセフ牧師がその兄柳ヨハネ長老に会いに行こうとする。38度線のすぐ上黄海道の、ソウルの西北方向にある小さな村、信川(シンチョン)、彼らはここで生まれ育った。朝鮮戦争時、この村でおおきな事件が起こりその当事者だった彼らは故郷を離れ、米国東海岸まで流れてきて40年経ち老年を迎えた。
ところでこの二人が主人公格なのだが、ヨハネ/ヨセフは似ていて紛らわしい。(ググるとヨハネには「神の国が近づいたことを人びとに伝え、悔い改めるよう迫った」洗礼者ヨハネのイメージがあることを知った。これは含意されていると思ってよい。)
キリスト教徒の多い地域であり二人の父も牧師だった。ここで、40年前(朝鮮戦争時)に惨劇があった。彼らはその目撃者ないし当事者だった。何十年も米国で暮らした後、ヨセフは北への旅行の機会を得るが、そのとき、自身と兄の当時の悪夢あるいは記憶がどんどん襲ってくる。重苦しい話ではあるが、事件の真相が少しづつ明かされるというミステリのようにも書かれているため、読みやすくもなっている。
日本敗北後朝鮮半島北部はソ連軍によって占領され、土地改革が実行される。大地主と企業家は先に南へ逃げ、中農と自作農が地域の上位階級になっていた。かれらはたいていキリスト教徒だった。村の作男や働き手だった小作農が、平壌に行って短い教育を受け村に帰ってきて、土地改革を実行した。差別されていた下層農民が先頭に立って暴力的に村の有力者の土地を没収する。激しい軋轢と憎悪が生まれた。南に逃げた中上層階層の子弟は極右団体を結成し、朝鮮戦争時、故郷に帰り旧秩序を回復しようとした。
「(朝鮮)戦争直前、北朝鮮全域のプロテスタント教徒は、三一節の行事と選挙不参加事件などによって、北朝鮮当局と関係が悪化している状態にあった。そのようななかで米軍が北進するや、信川、載寧(チェリョン)などのキリスト教徒の青年と右翼青年が蜂起した。最初は載寧で北朝鮮軍と党員がキリスト教徒を処刑して後退していったが、米軍が進駐する前に治安の空白地帯だった信川で立ち上がった右翼青年たちは、まだ後退できていない共産主義者とその家族に対して、報復的殺戮を加え始めた。」(黄晳暎『囚人』上p241)
私もそうだが日本人はだいたい朝鮮歴史の概要を知らないので、背景説明を少ししてみた。
2. 犬を吊り下げる
「エホバよ、主の大敵はみなこのように滅亡させ給え、彼らには哀れみを与えることなく全滅させよと言われましたが、イエス様は愛と平和を教えられました。繰り返して言いますと、我が故郷の土地を奪い、そこに住みついている彼らにも私たちと同じように霊魂があります。p9」
愛と平和という言葉に反し、「敵に哀れみを与えることなく全滅させよ」という命令にしたがったかのように、敵とみなした人々を次々と殺害していったそうした熱狂がかってあった。なにより「愛と平和」をめざしていたはずの信心深い若者たちが、殺人狂になっていくという地獄。遠くから垣間見ることさえ辛いそうした惨劇に、この小説は近づいていく。
柳ヨセフが見た夢の、どんよりした暗い夢のイメージが3つ最初に提示される。最初は意味がわからないのだが、最後まで読むとこの小説の重要なシーンであることがわかる。
最初のイメージ。
α「どんより曇った日であった。(略)
赤ん坊はシーツにくるまれておりシーツの端がひざ下まで垂れ、ひらひら舞っていた。(略)大人は赤ん坊を抱き上げ、木の一番下の枝に布でしばりつけた。p1」
残虐という以上になにやらひどく不吉なイメージである。この不吉なイメージは、この後も反復される。
β「むごたらしくもあり、血が騒ぎだすような興奮の中で私は犬が屠られる光景を初めて目撃した。犬の首に幾重にも縄を回し、ほどよい高さの木の枝にひっかけて吊り下げ、縄を引っ張る。ピンと張った縄をさらに引くと、犬は目を白黒させながら四つの足をジタバタさせる。p22」
γ「あのときオレはおじさんを電信柱に吊り下げたんだよな。p23」
αのイメージの意味は直ちには理解できない。ひと又は犬が木のようなものにくくりつけられるイメージがp22〜23に二つ出てくるのでβ、γとして、引用し考えてみよう。
βは、他人の飼い犬を吊るして食べてしまうシーンの一部。今では残虐無比と非難されるだろうが、この当時は悪ガキのいたずらとしてしかられる程度で澄んだのだろう。「血が騒ぎだすような興奮の中で」ひとは狂う、犬を屠るくらいならたいしたことはない。しかし人ならどうか。
γ、これは殺人のようだ。しかしこの頁では、幼い時にさまざまな楽しみを教えてくれたスンナムおじの亡霊との短い対話の断片として記されているだけなので、いったいどういうことなのか意味は分からない。
いったいどういうわけで、この小説はこんなふうにわかりにくい始まり方をしているのだろうか。この小説は、庶民がふとしてきっかけで大量虐殺を犯してしまうその謎を描こうとしたものだ。日本では関東大震災後に朝鮮人大量虐殺があったが、それを犯した人もちょっと前まで平穏な市民だったはずだ。
謎を謎のままで提示しなければならない。一方、読者の興味をつなぐよう、語り方に工夫が必要だ。そのためにこの小説は過去に殺されたたくさんの人物が亡霊となり、自由に現在にやってきて主人公たちと対話する、という形を取っている。主人公は過去に自分がやったことを記憶している。だがそれは思い出したくないことなので抑圧している。亡霊がやってきてひとことだけつぶやく。読者にはこの頁ではその意味が分からない。異様な感触だけを残して小説は進んでいく。
αについては、p41に説明がある。「大おばあ」つまりヨセフの祖母はこんなふうに言う。客人が流行り始めても田舎の村には医者もいない。巫祭(クッ)をしたくても金もない。(表題になっている「客人(ソンニム)」とは危険な伝染病だった天然痘のこと)何もできない。
「我が子が病に冒されるとただ胸に抱きしめていて、もう助けようがないとわかると草わらか雨具にぐるぐる巻いて夜更けに山に行くのさ。山に行って背の高い木を選んでその枝にしっかりくくりつけて降りてくる。カラスはまたなんであんなに多いのか、まだ死んでもいない体に集まってきて目ん玉を突っついて食べるんだね。子どもの父母が夜通し見守ってカラスを追っ払うのよ。そうやっているうちに助かった前例もあるので、みなで幾夜も木の下で見守りながら夜を明かしたらしいね。41」
子捨てと究極の祈りが合体しているような、ひどく奇妙な風習だ。生と死の距離が近く、まれに反転することもある幽冥の世界。
3,虐殺
信川だけでも三万五千人以上が死んだと言われているらしい。残虐行為の一角をこの小説から見てみよう。
「数十名の青年が畔に伏せていた。彼らはそれぞれ手に鎌や鍬や棍棒を握っていた。(略)彼らは駐在所の前まで来ると、うわーっと大声で叫びながらなだれ込み、建物の中でうとうと座って居眠りをしていた二人の署員を棍棒と鍬で滅多打ちにして殺し、奥の部屋で寝ていた署員も撲殺した。p218」
始めての殺害。駐在所員の殺害は蜂起としての合理性はある。しかし撲殺する必要はないわけで、そこには貧民による土地改革をどうしても許せないサタンの仕業と位置づける強い反動的情動があったと思われる。
また、直近に載寧(チェリョン)で党員と北朝鮮軍による殺害があった。それらに対する激しい報復感情が噴出したともいえる。
「彼らは、以前から反動だとにらんでいた家はもちろん、疑わしいキリスト教徒の家々を捜索し、相手がしたように家の中で家族らを残らず処刑した。(略)載寧(チェリョン)での三昼夜は、九月山(クゥオルサン)一体でそれから始まる血の惨劇の導火線となったのだ。p222」
「私たちがこの戦いの勝利を占める唯一の方法は、神の力に頼り正義のために悪を覆さなくてはならないという信念を堅持することだと信じております。いま自由のための十字軍は私たちを解き放つべく近くまで来てはおりますが、サタンの軍勢はいまだに私たちに脅威を加えております。(略)主イエス・キリストの御名においてお祈りします。アーメン」とヨハネは唱える。
仁川に上陸した米国軍という朝鮮戦争のヒトコマは、そのまま直接「自由のための十字軍」というキリスト教神学上の概念として受け取られる。であればそれへの加担は神の命令への服従に等しい。
そんなふうに彼らは、制圧済みの郡の党庁舎に集まる。
そこを拠点に「口ではとうてい言えないほど身の毛のようだつような残酷な」所業が繰り返される。(p229)
合理的な理由があってはじめられた残虐行為は、集団的熱狂のなかでどんどん凶暴さを加えていく。加害者たちはみずからの残虐さに慣れてしまい、反省することもなくなる。
「うるせえな。一人の男が赤ん坊をまるでサッカーボールを蹴るように蹴飛ばすと、赤ん坊は一瞬宙に浮いて二、三歩離れたところに転がり落ちた。p235」
ヨハネは幼い頃、近所のガキ大将株だったスンナムおじさんを捕らえる。最初にでてきた、犬を吊るして食べてしまうという乱暴な子どもの遊びを教えてくれたものスンナムだ。ただそんな思い出は今は関係ない。保安隊として村のリーダー格だった彼を許すわけにはいかない。
ただヨハネは彼を本部に連行するのは止める。連れて行けば、殺される前にひどい虐待や辱めを受けるだけだから。
「土手の上に電柱が見えた。 あれに吊り下げろ!(略)
仲間たちは電柱の足場に電話線を引っ掛けると容赦なく下に引き寄せた。クワッと異常な声を上げ足をばたつかせながらスンナムの体は宙に浮いた。p241」
スンナムは吊るされる。これが冒頭にちらっと出てきた γ である。
黄晳暎が、α、β、γと、ひと又は犬が木のようなものにくくりつけられるイメージを反復するのはなぜだろうか?
γは弁護の余地ない大虐殺の一部である。ここでの被害者はアカと呼ばれる人びとであり、加害者はキリスト教徒の青年団である。
三万人以上が死んだという大虐殺。その過半はキリスト教勢力から「アカ」に対する殺害だった。
その中の一つを黄晳暎は「男を電柱に吊り下げる」というイメージで描写する。そのγのイメージを説明するために、βがある。つまり虐殺はむごたらしいばかりではなく、「血が騒ぎだすような興奮」を誘い出す集団心理を誘発するものなのだ。昨日まで平和だった農民たちが、虐殺者集団に変貌する一つの契機を描いたものだろう。
αは虐殺を描いたものではない。民族文化の底辺にある「生と死の距離が近くまれに反転することもある幽冥の世界」を引き合いにだしたのは、βとは逆の要素、何らかの赦しへのきっかけを得たいという発想があるのであろう。
「恨みも怒りも解けてしまった」とこの小説は語りたがるが、それがとても困難なことだということも作家は知っている。なにより、事実を隠蔽したり、虚偽を展示することによってはそれは実現しないだろう。(ここでは詳述しないが、この大虐殺について北朝鮮当局は博物館まで作って展示しているが、虐殺者は米軍であるとしている。この本が語ることとおおきな違いがある。)
「男を電柱に吊り下げる」というイメージはまた、人間の罪を引き受け赦しを与えるイエスのイメージに近いともいえる。だが、糾弾、謝罪を求めるといったことを中止し、恨みと怒りの消失を求めるが、作家はキリスト教のような絶対的な赦しを約束しているわけではない。ほんやりとした方向性における一致以上のものはそこにはないと考える。
4 罪人と神
ヨハネが現地に残した妻の問いかけが哀切である。
「どうしてこんなにまでお互いを憎み合うようになったのか、それが不思議でね。植民地時代の日本人でもあれほど憎んではいなかったはずよ。
私一人がここに居残り、悪事を犯した罪人のように暮らしながら……いたいけな娘二人にろくなものも食べさせることができないままなくし、残ったあの子一人を何とか育て上げながら、いつも考えましたよ。神にも罪があるのではあるまいかと……p168」
殺人者の妻は差別されるべきか?殺されたものはいなくなり、殺したものも南へ逃げた。残されたものは殺されたものの遺族である。数少ない殺した者の家族は怨嗟、恨みのまとにならざるをえない。彼女自身が罪を犯したわけではないのに。
彼女自身が罪を犯していない以上罰や差別は与えるべきではないという理屈は、小さなコミュニティでは通らない。
「寒井里では、私たちは誰にも顔向けができなくて、長い歳月を罪人のように暮らしたんです p167」
「あの生地獄のような惨劇を、上からだまって眺めていた神さまにも罪があるのではあるまいかと、ずっと思ってきたけれど p168」
ヨハネの日々の殺害・暴行を知りながらそれを許していたのがヨハネの妻の罪である。それを彼女は40年間隣人から問われ続け、罪を認めざるをえなかった。では神は、唯一絶対にして褒むべき神は「あのような惨劇を上からだまって眺めていた」、それは罪ではないのか?
ここには、善である神が悪を許容するのはなぜか、という神学的問題には直ちには帰着させえない切迫がある。神が人格的存在であるなら、罪は否定できないのではないか?
「不治の病に犯されたとき、ヨブは神を怨んだけれども、敬虔なるヨブはこの苦しみでさえ神の恩寵だと悟」る。なぜ苦しみが恩寵なのだろう。
見ていて許容したことが神の罪であるなら、それは恩寵であるとはいえない。ヨハネの妻はたぶん耐えられなくなっただけだ。自分の不幸がなんの意味付けもされないままで、いわば生傷のままでさらされ続けることに。
「人間につきまとう苦難といえどもそれはある目論見をもった神から与えられたものでしょう。(略)私はいまヨブのように神を怨む心を捨て、人間が犯した怖ろしい罪を神のせいにすることはすまいとこころに決めているのです p169」
神を怨むならば彼女は今まで以上に何の寄る辺のない孤独に立ち尽くすしかなくなる。彼女は神を怨むのを止めることにした。あのような惨劇を行ったのは誰か?それは神ではなく人間である。人間が我が手でもって行った殺害はその人自身のものであり神のせいにしてはいけない。
ここで、「神に罪があるか?」から問題は転回されている。神を怨むことは実生活上彼女にとって賢い選択ではない。つまりヨハネは罪を犯した。ヨハネの妻も共犯者ではあろう。しかしそれだけであり、何十年も差別される理由にはならない。
「兄さんのヨハネが殺(あや)めた人たちはサタンではなく霊魂をもっている人間であったのです。兄さんのヨハネもサタンではなく信仰が捻じ曲がっていただけなんです。」
人が人を殺すことの罪は、その血痕は数十年経とうと消えずに残り続ける。事実を認めることは苦しい。しかし、避けようとしてもそれは、可能ではない。
「私、望むことなどありませんよ」何かを望むことに意味はない。「この世には人間どもが犯す罪に満ち満ちている」北朝鮮であろうと韓国であろうと統一国家であろうと「人間どもが犯す罪に満ち満ちている p169」以外の生き方は人間にはできない。
おそらく黄晳暎はここでそう言い切っている。これは怖ろしいことだ。なぜならそうなら例えば正義のために命を掛けるといった行為はすべて虚しい愚かな行為になってしまうから。この本には書いてないが、黄晳暎はかの金日成と何度も親しく対話したことがある少数の韓国人の一人である。どこから見ても罪の塊である金日成と会食するなど犯罪であろう、そうした意見には一理どころではない重みがある。ヨハネの日々の殺害・暴行を許していたヨハネの妻に罪があるのと同じである。多くの強制収容所を経営し、収容者に死に瀕した生を強いている金正恩は断罪されるべきだ。しかし、彼をサタンであると信じ、なんとしてもその死を願うことが正しいのか?正しくはない。金日成も金正恩もサタンではなく信仰が捻じ曲がっていただけにすぎない。敵対し粉砕を叫ぶことは政治的行為としてありうるが、その有効性は状況に於いて問われる。つまり絶対的なものではない。
「少しずつでもそれをなくしながら生きていかなくては……」つつましやかな願い。しかしそれを捨ててはならない。しかもそれを貫くのには非常な力量が必要だ。
「お祈りを上げましょう」
「この共和国においても、主の御恵みのもと人びとが健やかにそれぞれの生を営んでいる ことを確かめることができました」そのことを心より感謝いたします。
(このフレーズは、黄晳暎から韓国国家へのメッセージでもある。共和国市民も本来は自分の国家の成員であると主張している韓国は当然、皆が「健やかにそれぞれの生を営んでいる」ことを確認し祝福すべき立場である。しかし北共和国だけでなく韓国も両国の往来を厳しく制限している。(ドイツ人や日本人は両方の国に入れるのに)黄晳暎は1989年北朝鮮を訪問し、帰国すると入獄させられるので海外を放浪し数年後帰国入獄した。わざわざ隣人の生存を見に行った黄晳暎を罰そうとする国国家はオカシイ!)
神に感謝すること、たとえ神を信じていなくとも。そうしないと生きていけないから、作家はそう言っているようだ。
「怨恨ゆえにまだ虚空をさまよっているだろう多くの亡霊たちが安心して旅立つことができるように、シキム(死者を送り出す巫儀)でもしてあげないとね。スンナミおじさん、一郎おじさん、朴明善のうちのチンソン、インソン、ヨンソン、トクソン、チュンソニおじの内儀、小学校の女の先生、そしてあの倉庫のなかでもだえ死んだ多くの人たち……」
亡霊たちは安心して旅立つだろうか?「安心して」なんてことはありそうにない。そうだとしても私たちは祈る。祈らなければ耐えられないから。
5 赦すこと
1950年10月19日、中国人民志願軍参戦、12月6日には平壌奪還。人民軍はどんどん南下してきて、信川のあたりもすでに敵の勢力下になり、ヨハネは逃げるため久しぶりに家に戻る。
「私(妻)は全身汗まみれで、顔からは汗が滴り落ちていた。
「子どもが生まれるわ」「なんで選りによってこんなときに」(略)
夫は周りを見廻すと、乱暴に箪笥を開けた。服がこぼれるようにあふれでた。その衣類の中から肌着を一枚取り出して彼は子どもを取り上げた。赤ん坊の泣き声と彼の歓声が聞こえた。 p182」
しかし、すぐ近くで銃声がし、彼はそそくさと立ち去る。夫はずっと遠くに去っていってしまった。
数十年後、ヨセフは兄嫁を尋ね、このときの肌着を託される。
「寒井里に行ってその骨を埋めるときに、これを燃やしてから一緒に埋めてちょうだい。 p179」
「彼は雑草が生え茂った場所を避け、乾いた土が露(あらわ)になっている所を選んで蹲った。手でそこの土を掻き集め、ほんのりと芳しい匂いを嗅いでみる。」
そこに古枝を集めて火をつけ、兄の肌着を燃やす。
「兄は故郷の地に戻ったのである。p282」
遺体に火をつけ燃やし、故郷に埋葬すること。それはかなわなかったにせよ、彼が一生抱き続けた深い深い罪を追体験し祈ることで、ヨハネは故郷の地に戻る。
「ヨセフは壁伝いに長く列になって立っている亡霊たちを見廻した。およそ十人くらいいるように見えた。
(略)
おれたちはヨハネを連れて行く前に、彼が殺めた人らを解き放してやろうと思って集まったのだ。人は死ねば、犯した罪はみな消えるというが、あったことの真相をありのままに明かしておかなければならないのだ。p215」
ひとはともすれば謝罪や赦しをめぐって大騒ぎしてしまうが、「あったことの真相をありのままに明かしておくこと」を十分に確認せずにそうしたことをしても結局無意味である。(口にしたくないほど愚かしい「慰安婦問題」をめぐる日本側の態度をみてもそのことは明らかだ。)
「あったことの真相をありのままに明かしておくこと」をまず求めなければならない。
「殺した奴も殺された奴も、この世を去れば、みーんな一つのところに集まることになっているんだよ。(略)
やっとのこと故郷に帰って来てなー、昔の友だちにも会い、恨みも怒りも解けてしもうた。 p278」
こう言っているのはヨハネ(亡霊ではあるが)である。ヨハネの殺人者としての所業を知ったわれわれは、こうした言葉だけではなかなか納得しずらい。加害者がそう言ったからと言って、被害者は恨みも怒りも忘れないのではないか。
しかし、この小説では、被害者であるスンナムおじさんや一郎(イルラン)も亡霊としてそこに居る。
「さあ、さあー。もうこれでいい。早よう立たにゃ。 一郎も同意した。 そうだ。みんな一緒に立とう。」
40年亡霊として彷徨った後、加害者ヨハネが亡霊として故郷に帰ってきた。それによってやっと立ち去ることができる。恨みも怒りも解けたというのが本当かどうかは分からない。しかし彼らは実際には既に死んでいるのだから、「去るべき者らは去り、生き残った者らは新しく出発しないと。p279」ということはできる。
最後の章は「締めの歌」である。
民族に自由が戻り/働く者が権利を手にしたとき/人として生まれた幸せが分かった/しかしそれも束の間/自由も権利も/一場の夢と化し/命まで奪われてしまったのだ
恨みはあろう悲しくもあろう/しかし今はもう/怨みも悲しみもすべて忘れ/安らかに心おきなく/あの世の方へ/去られ給え、旅立ち給え
最後に、一転してキリスト教徒と対立した労働者の側、被害者の側の恨みが唄われる。「怨みも悲しみもすべて忘れ」というのが正しいのかどうか私(野原)は分からない。
韓国はシャーマニズムの伝統がある。ムーダン、マンシンとよばれる降神巫。彼らは人びとから依頼を受けて、死者をあの世に送る儀礼を行う。これがクッとよばれる。厄払いである。
死者とその怨念、彼に向けられた怨念その両方を彼方に送るための儀式。その様式を借りてこの小説は書かれた。
「怨みも悲しみもすべて忘れ」は黄晳暎の意志ではなく、クッを必要とした民衆の意志である。
6 怨みも悲しみもすべて忘れ
この小説のなかでは、40年前に死んだ死者たちと先日死んだ死者がともに亡霊となり、生き残った人々と対話する。死者たちに語らせる。それは40年間彼らの声が抑圧されなかったものとされてきたからだ。
殺害された者はもはやいないので発言できない。殺害したものも逃げてしまい故郷との繋がりが失われる。また殺害したものは真実を語るのは自分にとってつらすぎるとして抑圧してしまう。
しかし実は小説家はどのような人のどのような行為であろうと小説に書くことができる。40年前の世界も現在の世界も。しかし黄晳暎はそのどちらも選ばず、現在に浸透してくる過去を描いた。
40年前を描いた小説であってもそれが読まれるとしたら、現在にしか生きていない読者がそれを求めるからだ。ふと思い出される過去の記憶といったものは現在の少なくない部分を占めている。40年前の過去であっても、トラウマと呼ばれる抑圧された記憶はふとしたきっかけで鮮明に思い出されることがある。40年前の事件のドキュメントが求められているのではない。事件のドキュメントの意味が求められているのだ。殺す者と殺される者の距離、40年間という距離、国家と民衆の距離、そのような隔たりを超えるために、亡霊による語りというスタイルを黄晳暎は採用した。
最も抑圧しようとしたものは何十年経っても残る。小説家としてそれを書こうと思ったのは当然だろう。
しかも重要な出来事でありながらその真相が隠蔽されているのであるから、政治的、社会思想的にも是正されるべきである。しかしそれは、北朝鮮国家と韓国市民の多くの両方に正面からケンカを売るに等しい行為であり、大きな問題を引き起こす可能性があった。半亡命の身分にあった黄晳暎にとっては、なおさらである。しかし実際にはそのような真相を明確に突き出す作品を彼は書いてしまった。半亡命→帰国・入獄から1998年出獄、その5年後にやっと書き上げたのではあるが。
「この作品に描かれた惨劇は民族内部で演じられたものであるだけに、北側の公式的な主張を立場とする人たちからも、また惨劇のあと北の地を離れ南に移ったクリスチャンを中心とする人たちからも、否定され指弾されるということはありうるだろう。(p291)」
そうした自己保身的あるいは政治的配慮よりも、作品を完成させることだけを目的に黄晳暎は書き上げたのだ。
「キリスト教とマルクス主義は、この民族が植民地時代と分断の時代を経てくる間に、自律的な近代の達成に失敗し、他律的なものとして受け入れた、近代化への二つの異なった途であったということができよう。」
最近翻訳がでた自伝『囚人』に詳しいが、1985年から1993年まで黄晳暎はドイツや米国などに滞在し、途中何度か北朝鮮も訪問した。1980年代の西欧から見た場合40年前の北朝鮮のキリスト教とマルクス主義はほとんど双生児のように似ていると見えたことだろう。「キリスト教とマルクス主義は考えてみれば一つの根から生えた二つの枝であったのだ。」日本の場合では大学に行ったりするインテリが明治時代にはキリスト教に、それ以後はマルクス主義にかぶれるといったふうに現象した。急成長する資本主義の大きな矛盾とまだ封建的な伝統社会の抑圧、その双方を批判する武器として使われたのだ。おおざっぱに言えば、同じ社会集団に時期をずらして受容されたためお互いの大きな争いは起きなかった。
朝鮮では、光復後に何もない所から国家を作らなければいけないという機運が高まり、その要請に答えるイデオロギーとしてキリスト教とマルクス主義が、それぞれ別々の階層に選ばれた。そして不幸なことに二つのグループは激しく対立し、ついにこの本に書かれたような巨大な惨劇を産んだ。
AがBを撲殺する。その意味ははっきりしている。ごまかしようがない。しかしキリスト教とマルクス主義が関与すると少し違う。同じ殺害でも神のため、あるいは党のためであれば許される場合もあるのだ。この小説ではもっぱらキリスト教徒が扱われる。彼らが天国に通じる道と信じて殺害を行ったがその道はわずか数ヶ月で消えた。彼らは故郷から逃げざるを得なかった。神のためという言い訳が通用しなくなり、殺害という苦い記憶を抱えてAは40年生き続ける。しかし黄晳暎は悔恨や反省を一切書こうとしない。
AがBを撲殺した。Aはそのことを忘れない。不快なもやもやとして、強い苦さとしてそれはときどきやってくる。それを悔恨や反省としてすこし意味を変え昇華していくことが、人間の文化だろう。それを最も洗練させたものがキリスト教とマルクス主義(そして近代文学)だろう。反省、神への帰依によって救われること、それは「神の名によって殺すこと」とそれほど大きく違うだろうか?黄晳暎はそこまで書いていない。しかし、彼が悔恨や反省を書こうとしないとはそういう意味でもありうるだろうか。
BはAに撲殺された。Aのようなそれ以後の40年はBには存在しない。亡霊として漂い続けただけだ。BはAを激しく怨んでいるはずだろう。しかし厳密に考えるならばその怨みも、生きているB以外の人がなければならないと強く考えているだけなのではないか。Bはただ死んでしまい何を考えているのか分からない。
「強い風が吹きまくっている。」
「一群の人びとが上半身を屈め、同じ方向に進んでいる。何か重たいものを引く網でも肩にかけているような姿勢なのだ。前進している人の長い列は前の方も、後ろの方も終わりが見えない。曲がりくねった道は野原を横切り、遥か彼方に見える大きな山並みに接しているが、人びとは一切無言である。屈められた彼らの背中が見えるだけである。」283
彼らはただ歩いているだけなのか。彼らのうち少なくない人は、自らその手に凶器を担い他者の肉体にそれを振り下ろした。見えはしないが、人びとはその罪とともに歩き続けるのか?
一方「自分はそこに現れた一幅の画面の上を、鳥のように飛翔していた。」
鳥のようなのはおそらくヨセフではなく、作家黄晳暎であろう。殺された者も殺した者も、決してエリートでもインテリでもなかった。広大な歴史の原野をただ歩き続けるしかない庶民である。しかし作家はそうではない。そう望まなくとも作家はすべてを見通し設計しうる。語られる限りでは歴史すら、改変し各自の感情、倫理的色合いすら左右できる。読者も巻き込んで。
殺害者にもっと真摯な反省を求めるという感情を読者は持つだろう。大きな虐殺事件でありその事実を明らかにし、悼むことは必要だ。
それに、加害者を加害者と名指すことは必要だ。つまり、反省と謝罪を求めることは。それは一方の側に加担することになり、政治に巻き込まれることになる。
ただ、文学の役割はそれとは違う。「遠くの方から牛の鳴き声と、首につけられた鈴の音が聞こえてくる。めんどりが卵を産み落として出す姦しい啼き声も聞こえてきた。田園がひろがる野原では、人びとが田植えの歌を歌っており、それにまじって、鉦(ケンガリ)や長鼓(チャング)を叩く農楽(ノンアク)の音も聞こえてくる。」
数多くの殺害を飲み込んでなお、庶民(常民)の世界は延々と続いていく。無理やりであろうと「怨みも悲しみもすべて忘れ」という言葉とともに、作家は彼らに別れを告げる。
(2010.2.5)