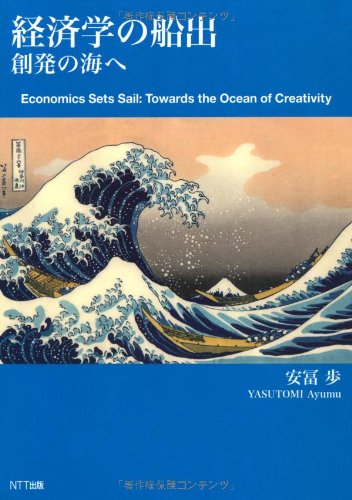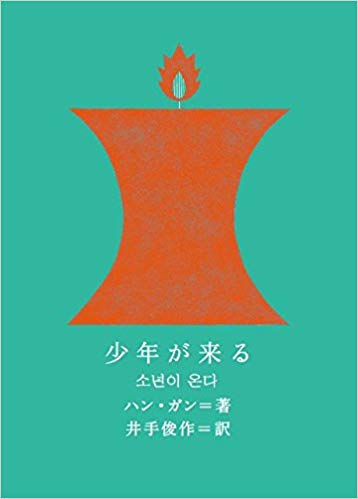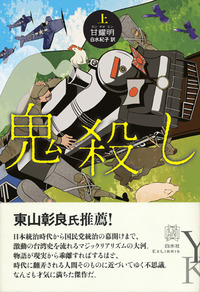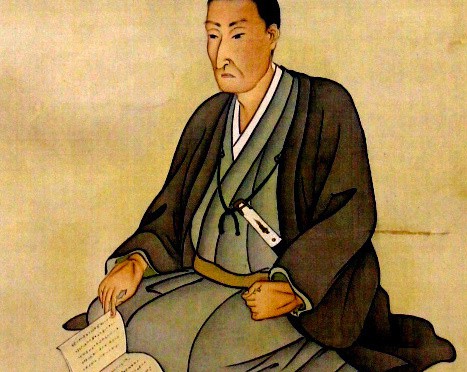1945年5月17日から6月2日に4回、日本軍から米軍捕虜の提供を受け、九州大学医学部第一外科と第二解剖学教室第二講座が死に至る生体実験を行った。被害者は墜落した米軍機に乗っていた兵士8人である。
この事件についてのいままでの著作は、主に公判記録及び公判に関する宣誓供述書に基づいていた。非公開であった再審査関係の膨大な資料を(国立国会図書館から発掘し)精査してまとめたものが、熊野以素『九州大学生体解剖事件』(岩波書店2015年)である。
この事件の主犯格の、石山教授と小森軍医見習士官は裁判当時すでに死亡していた。そこで、事件の大学側関係者は鳥巣太郎助教授、平尾健一助教授、森好良雄講師とされ、3名ともに死刑が宣告される。(後に減刑)
この本は、著者の叔父である鳥巣太郎(鳥巣と記す)を中心に記述される。
裁判の経過のなかで鳥巣は事件を反省する。その核心は次の二つの引用にある。
A)「林先生の証言は、その一言一言が私の肺腑を突き沈痛な思ひに悩みはつきず。げに真理は簡単である。私が参加したことに対する如何なる弁明も、何の訳にも立たぬことを改めて認識した。(略)
又しても「当時何故もっと意志強く迫らなかったか」といふことが今更ながら未練がましくも残念の極みである。」(48年5月林春雄証言を聞いて) p114
B)実際には、鳥巣は石山に次のように言った。
「先生、また、先日のような手術をなさるのですか?(略)
あのような手術は軍病院でするべきではないでしょうか。もし手術に九大が関係しとるということがわかれば、後で大変なことになると思います。(略)」 p34
鳥巣の行為・思想を中途半端だと指摘することはできる。一回目の実験に立ち会う際、彼は事情を知らなかった。しかし二人目の兵士の手術時、彼は理解していたのに手術を助けた。二回目の手術の前、鳥巣はB)発言をし、手術には遅れていく。しかし参加はした。
いずれにしろ、手は汚れていることになる。
戦争は日本の敗戦で終わり、捕虜虐待に厳しい裁判で臨むGHQの支配下、1946年7月鳥巣は石山教授外3人とともに逮捕される。石山は後に自殺。
鳥巣にとっては、生体解剖(殺すこと)への拒否が第一順位であり、同僚も内心では当然そうであったはずだと思っていた。しかし同僚は実際にはB)の行為は取らなかったわけであり、自己保身を第一順位にすることにさほど疑いを持っていなかったかもしれない。仮にそうであったとすると、戦後は逆に、自分がB)に限りなく近かったことが有利になる。したがって、B)に限りなく近かったとみずから思い込むまでに自己を偽り、そのように鳥巣にアピールしたこともあったかもしれない。1949年5月に「我々は石山教授に手術をやめるように頼みに行った」と鳥巣が書いたのも、そうした働きかけの結果だったかもしれない。
B)の立場に立つことは一生、「今更ながら未練がましく悩み続ける」ことである。
言葉で説明することは理を通すことであり、A)のように語らざるをえない。それはしばしば、割り切れないものである現実に厳しすぎる裁断をするものだと感じられる。
鳥巣の場合は、目の前の手術台に横たわった身体に対する犯罪という具体的なもので、戦争犯罪といった大きな主題にかかわるものではない。医師としてその命を殺す実験に関与するという問題は、ある意味で殺人という倫理的問題を、手術台の上に展開し詳細に再体験することを迫る。
そのなかで、鳥巣はA)とB)のあいだでぐるぐる思索し続ける。
しかし、同僚たちは違う。彼らは事件時、ファッショ的専制的な主任教授に逆らうことができず、裁判においても鳥巣のようにB)のような減刑要求する根拠もなかったため、「反抗は許されず仕方なく参加したのだ」と情緒に訴える弁護に頼るしかなかった。
しかし獄外の同僚の家族たちや大学関係者たちは、一致し熱心に弁護士に働きかけた。それは家族としては当然のことであっただろう。しかし、軍とその影響下にある大学という専制的男性リーダーの下にあったホモソーシャルな支配の構図が、問われなければならなかった筈だ。だが、問われるべき主犯である主任教授石山は、卑怯にも自殺してしまう。従犯たちは、自己を「支配の構図の被害者」に位置づけることにより、その構図を結局敗戦後まで生き延びさせてしまう。
閉じ込められた鳥巣はA)とB)のあいだをぐるぐる回るばかりで、自分を救おうとすることに熱心にならない。ただB)という行為をした自分を肯定しており、それをしなかった同僚を助けてあげなければいけないと思い続けていた。
この本は『九州大学生体解剖事件』という題で、題の印象からもいままでの紹介からも重く苦しい主題を扱った難解な本という印象を受けてしまうだろう。
しかしそうではなく、これは(むしろ)苦境におちいった幼子を抱えた若い妻が信じられないようなエネルギーで、横浜裁判当局に挑み、誤審を訂正させるという、日本には珍しい(米国人好みの)正義のヒロインの物語なのである。
ヒロインは鳥巣太郎の妻、蕗子である。鳥巣は最初の事件の後、妻に事件を打ち明け、大学を辞めたいとまで言う。蕗子は思ったことをまっすぐに口にする性格だった。
「石山先生がまた捕虜の手術をされるようなことがあっても、あなただけは決して手術に参加なさってはいけません!もし私が、米国軍人の妻でありましたなら、なぜ夫は手術されたのだろうか、手術されなかったら自分の夫はシナなかったかもしれないと思います。戦争の最中でも、米国軍人の捕虜を医学の研究に使ってはいかんと思います。戦場で軍人が殺されるのは仕方ありませんが、手術で死んだらお気の毒です。」p32
48年8月、判決。鳥巣外2名の医者と2名の軍人は絞首刑と決まる。鳥巣の予想外のことだった。蕗子は独力で嘆願書を作る。またその後では英語が達者な三島夫人の力を借り、二人で総司令部法務局に何度も何度も説明に行く。事実関係の細部についての説明。「初回の手術は参加はしたが執刀はしていない。鉤引き、血を拭うなどの補助を行った」「2回目の手術の前に石山教授に手術の中止を諫言。手術場には遅れて行った。」「三回目の手術は参加を拒否」などなどである。
これらの事実は、ここまではやらなかった、と否定により減刑を獲得しようとするものだが、本人にとっては、ここまではやらなかったがここまではやったのだと、思い出したくない犯行を再確認し反芻する効果がある。
蕗子は、実験遂行へのためらいを一言も口にしなかった同僚と鳥巣の差異であるB)にこだわる。そうしないと鳥巣を救うことができないし、なによりそれは事実だから。
事実関係の細部に焦点を当てて再審を勝ち取るべく書類を積み重なることは、同時に鳥巣にとっては、自身の倫理的反省がただの反復に陥らず、常に痛みとともに反省を深めていく効果を持ったと考えられる。
一人の人間を医療行為をすると言って騙して麻酔をかけ、そのまま材料として生体実験してしまう。これはいかにしても弁護できない絶対悪である。これが、A)の思想であり、無限性の責任論と名付けることができよう。
B)は、それに対しておずおずと違和感を提出したという行為である。きっぱりとした反対の意思表示ではないが、その時点の鳥巣のせいいっぱいの意志表示であった。それは服従と反抗の二つのベクトルの折衷であって。それを有限性の責任論と名付けることができる。
鳥巣たちに対する判決は1948.8.27だが、再審査の嘆願が粘り強く行われ、1950.9.12減刑決定。1954.1.12満期出所となっている。
わたしたちが現在この問題を考える時、戦争中(8.15まで)、占領終了まで(1952.4.28まで)及びそれ以後という3つの時期におけ評価がどう変わるのか、という問題も合わせて考える必要がある。鳥巣たちの裁判は刑法犯罪であり、戦中の日本、GHQ、戦後日本という国家支配者の差異によって、基本的には判断が変わるものではない。また、サンフランシスコ講和条約11条には戦争犯罪法廷の判決を受諾し、刑を執行する旨定められていた。
しかし、占領終了後すぐに強力な戦犯釈放運動が起こった。戦争中の政財界や軍の指導者たちを幹部とする戦争受刑者世話人会が作られ、「戦犯は戦争犠牲者だ」が国民全体に浸透した(三千万人の署名が集められたという)。
戦争指導者も末端の兵士も同じ、戦争の犠牲者であるという思想は、「先の戦争」の遂行責任を明確に追求しなかった。反省が行われるときはかならず「戦争だけはしてはいけない」「すべての戦争は悪である」と戦争を主語にした、(日本人は苦手なはずの)宗教的なまでの大きすぎる思想が語られた。憲法9条に結晶したこのような反戦思想は貴重なものではあるが、軍隊の全廃というテーゼは冷戦のなかで貫かれることはなく自衛隊が誕生し、時代とともに成長していった。
「講和恩赦と1953.8.3の戦犯赦免決議によって、満期を待たず戦犯は次々に釈放されていたのだが、鳥巣は満期まで務めることに強い思いを抱いていた。」p187 とある。 占領軍がいなくなればたちまち消滅してしまう「反省」、そのようなものとともに鳥巣は生きたわけではない。
わたしたちの70年の経緯を考える時、A)の思想の正しさが、抽象的な「戦争はいけない」という命題になり、時代の移り行きとともに、その背後に裏打ちされていた、殺し−殺された身近な人の体験をまるごと裏返すかのような荒業といったものがほとんど蒸発してしまい、力を失っていったのだと考えることができる。
それに対して、鳥巣の場合は、B)有限性の責任論の立場をたえず参照することを強いられたがゆえに、自己身体から遊離した正義の立場に立ってしまうことはなかった。無限性の責任は有限性の責任論に裏打ちされてこそ、真の反省として持続しうるのではないか
今では忘れられてしまった、生体解剖事件犯人とその妻の話。そこには小さくとも本物の反省があった。
「大東亜戦争(アジア太平洋戦争)」という巨大な悪を巨大な悪として反省しようとすることは、それがいかに真摯に行われようとやはり限界があり、有効期限切れが来たかのような現在である。
そうではなく、ひとつの事件におけるほんの小さな反抗、それを大事に育てることにより、事件全体へのトータルな反省に鳥巣がたどり着いたという実話。
それは、わたしたちの戦争体験の総括の失敗という課題に、光を当てるに足りるエピソードだ。