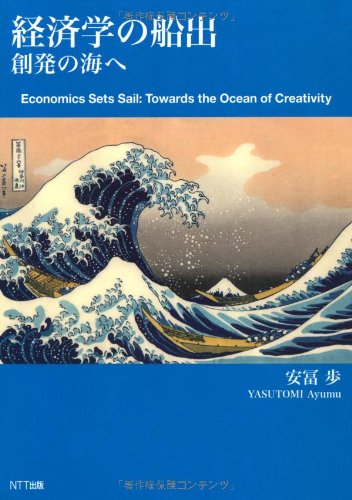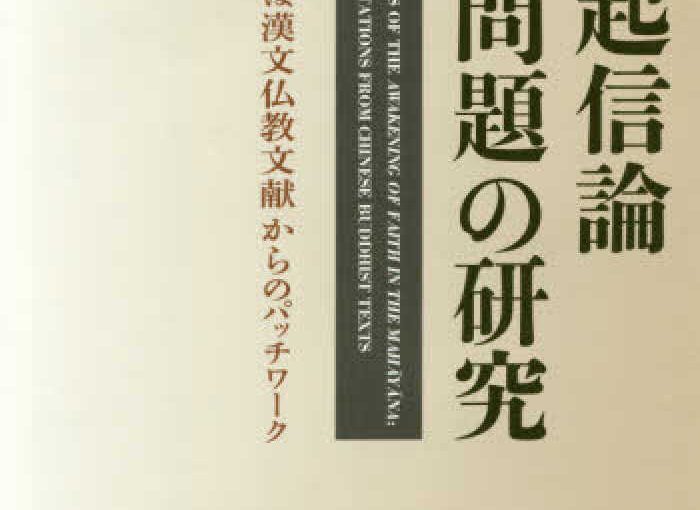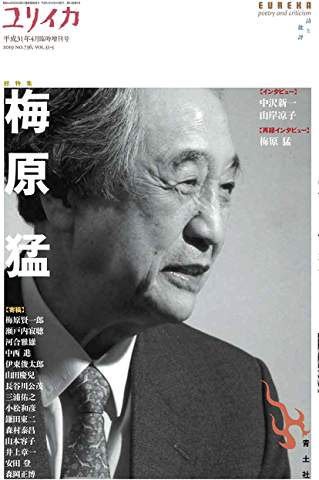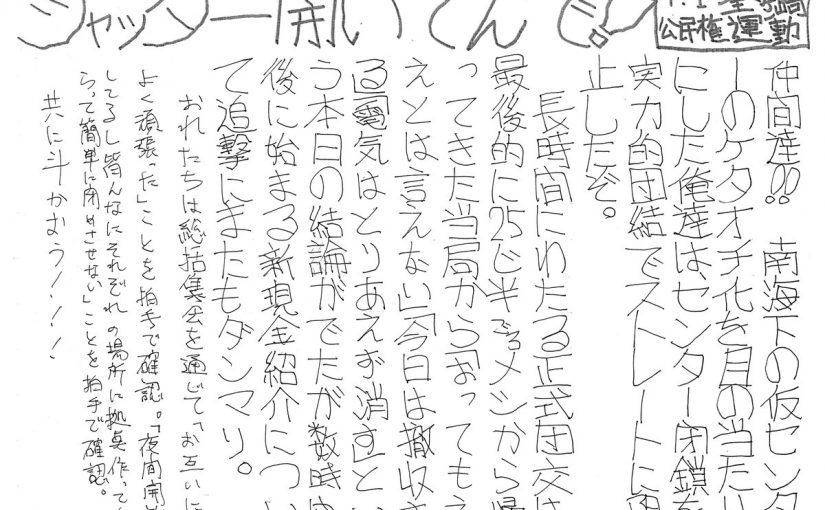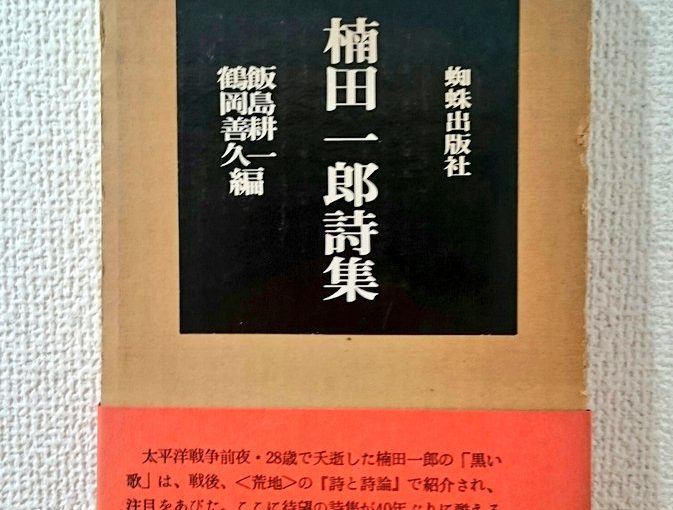「韓国「元慰安婦会見」めぐる議論、6つのポイント」という論説を、徐台教氏が下記サイトに書いている。
https://news.yahoo.co.jp/byline/seodaegyo/20200514-00178504/
徐氏の文章は分かりやすく妥当なもののように思われた。この問題について深く追求していこうとは思っていない。ただ徐氏の文章を読んで、思ったことが少しあるので書き留めておこう。93年河野談話以降日本国内の問題はあまり変わっていないし、日本国内を変えられなかった私の責任(李容洙さんと尹美香さんたち、に対する)もないことはないからだ。メモ的な形で恐縮です。
(1)寄付金に関する疑問
あまり興味がない。
(2)市民団体と被害者の関係性の難しさ
これよりも大きな問題は、ネトウヨあるいは日本の官邸周辺もかって無学だった元慰安婦たちの主体性・思想性を認めようとせず、正義連などに操られているとしてきた。あるいは金さえやれば黙るだろうとして黙らせたりしてきた。それでもだめなら無視し(橋下氏の場合)、死ぬか呆けるのを何十年もひたすら待ち続けた。
(2-2)
脱北民と韓国の北朝鮮人権運動団体との関係と同じように、当事者と運動団体のあいだでは、当事者は団体に利用されたという関係に陥りやすい。当事者は深いレベルで彼女自身に固有の恥辱や被害を語ることによりある意味で見世物になり続ける。一方運動団体は運動の利害、獲得目標、主張に一貫性を持たせるための論理の整合性といったものを大事にする。この限りでこの対立は普遍的なものだ。
(2-3)
普通10年もやっていればそれなりの成果は出るのだが、慰安婦問題は、「解決できない日韓歴史問題」にリンクされてしまい解決できなくなった。このことの責任は、第一義的に「解決できない日韓歴史問題」にリンクさせる方が、排外主義を煽り政権の支持につながるとする安倍政権にある。
(3)韓国保守メディアの狂騒
「朝中東」と称される朝鮮日報・中央日報・東亜日報の保守紙系メディアは、重大な「戦時性暴力」を追及する正義連の運動を「日韓関係の妨げとなる」と下に見てきた。ネトウヨは、嫌韓派として場合によってはかれら「保守派」を強く非難してきたのに関わらず、文在寅政権になってからは彼らの文在寅派批判を自らの嫌韓の素材にするという器用なことを熱心に続けてきた。
今回の反尹美香・反正義連の一大キャンペーンについても、おお喜びで引用し続けるのは間違いない。
しかしながら、李容洙氏本人の最大の恨みの対象は安倍首相とそのフォロワーであるというものごとの根本を無視して、喜んでみても騙せるのは愚かな人だけである。
(4)「親日・反日」フレームの間違い
与党の一部や熱心な文大統領支持者たちは「正義連批判=日本擁護=親日」というフレームで、「保守派」を批判する。しかしそれは違うだろう。
李容洙氏の真摯な告白を「保守派」が反文在寅運動に利用しようとしているだけだ。
「正義連が日韓関係を邪魔している訳ではないという認識を持つべきだ。」にも同意する。
(5)正義連も一つの契機に
30周年を迎えた正義連、という言葉を見る時、30年も解決しなかった「慰安婦問題」の愚かさを改めて考えざるをえない。93年の「慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送については、旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与した。また、慰安所における生活は、強制的な状況の下での痛ましいものであった。」「歴史の真実を回避することなく、むしろこれを歴史の教訓として直視していきたい。」を言葉通りに実行しておれば、こんなことにはならなかったはずだ。すべてネトウヨが悪いのである。
(6)「理解」できる関係を内外に
「30年間、過去のトラウマと闘いながら時には被害者として、時には運動家として責任追及運動を続けてきた李容洙氏が抱える苦しみはどれ程のものか。」温かい理解を徐氏は要請する。わたしも考えてみたい。
徐氏によれば、異常なまでの攻撃性を持つ韓国の保守メディアというものがこの問題のポイントの一つであるようだ。その問題についてはよく分からないが、韓国の保守派と日本のネトウヨの連帯というものがもしあるとしても、それは慰安婦問題はもとより、日韓友好にも役に立たないものだろうと思う。